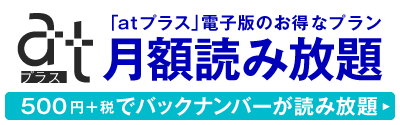桜井厚と谷富夫──生活史第2期
いま日本で生活史といえば、桜井厚です。これが、日本の生活史の第2期です。ほかに、谷富夫というひとも一派を築いていますが、これはあとで説明します。
桜井厚は現象学の研究からスタートしたひとで、中野卓の弟子です。日本に生活史を根付かせた中野卓のあとを継いだのが桜井厚です。南山大学の助手のときにアルフレッド・シュッツの翻訳なんかをしています。原著が2000ページもあるトマスとズナニエツキの『ポーランド農民』の抄訳もしてるんですが、いちばんつまらないところを訳している(笑)。『ポーランド農民』を読むなら、英語のダイジェスト版が出ているので、私はそっちをおすすめします。
1985年に、日本解放社会学会というものができます。流れとしては、学生運動や新左翼の流れと近いといっていいかもしれません。中心になったのが、青木秀男さん、福岡安則さんなどなど。大御所ですね、みなさんいまもお元気です。青木秀男先生は私の個人的な師匠だと思っています。青木先生からは、ほんとうにたくさんのことを学びました。
解放社会学会のメンバーが、学会をつくったあたりで、ある被差別部落の調査をします。そのなかのメンバーが桜井厚でした。同和対策事業がすでにはじまっていたはずですが、そこはとても貧しい村でした。そのときの様子は、『被差別の文化・反差別の生きざま』という本になっています。
そこで桜井厚は部落に出会って、中野卓の影響もあって、部落のライフヒストリーを聞くプロジェクトをしていく。おもに、関西の部落に入っていきます。そして、『語りのちから』という、すばらしい本を書きます。この本はほんとうにいい本で、日本の生活史調査の代表だと思います。
その後、最新の社会学理論──ナラティブ研究とか構築主義とかポストコロニアルとかフェミニズムとか──をとりいれていって、独自の「対話的構築主義」を打ち出すんです。いま、桜井厚の『インタビューの社会学――ライフストーリーの聞き方』はひとつのバイブルになってます。これが「第2期生活史研究」の代表作です。
桜井厚が主張したのは、語りを事実に結びつける実証主義は、ある種の暴力であるということです。実証主義は、分析の対象を一般化するから、暴力なんだというんですね。差別と戦うために研究をやっている以上、差別を再生産するような、暴力を内包するような方法論は採用できないと。議論がすごくリフレクシブ(再帰的・反省的)なんです。政治的認識関心を、理論枠組みと方法論にまで適用したんです。
方法論のレベルまで倫理的判断をつきつめて考えていった結果、暴力を行使しないような方法論を考え出したんです。これが「対話的構築主義」です。この方法論はものすごい広がっていて、いまだに院生なんかは桜井厚の本から出発します。
桜井厚は、「語りは語りだ」というんですね。極端にいえば、現実と関係づけるな、と。彼は、もう自分はある語りが事実かどうかということは考えないようにする、と宣言しています。それらを結びつけて考えるのは古いということですね。
じゃあ、具体的にどうやってやればいいのってなりますよね。桜井厚の有名な論文があって、滋賀で聞き取りをしたときに、こっちが聞きたいことばかり聞いてしまって、相手のしゃべりたいことを阻害してしまったと。でも、そのおばちゃんが「警察の尋問みたいやな」っていいかえす。このようにして、現場のリアリティは相互に構築された、という話をするわけです。
確かに、インタビューって、絶対そうなんです。こっちが聞きたいことを聞こうとするけど、向こうはしゃべってくれない。そうやって、お互いつくってるかんじ。「対話的」構築主義というのはそういう意味です。インタビューを、何かを一方的に聞き出す場ではなくて、聞き手と語り手との対話の場面だと考える。そのこと自体はそれで正しいですが、たとえば「この会話のなかで『部落』という言葉がこのように使われました」という分析はできますが、そこから「ここの部落はいまこういう状況にあります」ということを述べるのは非常に困難です。そのふたつは、理論的水準がまったく異なるからです。後ろを向きながら前に進もうとするようなものです。あるいは、「字を書くこと」に集中しながら「文章を書くこと」をしようとするみたいな。わかりにくい例えですみません(笑)。
それって語りそのものについての理論であって、調査の対象は部落じゃなくてもいいわけです。何の語りでもよい。桜井厚は、インタビューが共同で構成されるということを強調するあまり、語りと事実とを切り離してしまったんですね。部落のことはそれで何がわかるかというと、何もわかんない。ただ、「部落という言葉」がどう使われたかということしか分析できないんです。
社会学の存在意義
私自身、方法論の勉強は桜井厚からはじめて、とても大きな影響を受けました。でも、やってるうちに「これで沖縄は書けないな」って思ったんです。彼の方法をとると、ひたすらインタビューの現場で何が起こったのかという話になってしまう。それだったら、沖縄じゃなくてもいい。他ならぬ沖縄の調査がしたいのに。
対話的構築主義の立場では、現実のことを書かないわけです。現実のことを書いたら(一般化してしまうという意味で)「権力作用」になるから。だから、桜井厚のように現実と語りを切り離してしまう。それは、結局、社会のことを書かない社会学者になってくるわけです。語りのなかに社会があるんだ、という理屈になってくる。それによって、実態調査ができなくなっていったわけです。
私たちは「他ならぬ」ある特定の問題に(非政治的に)コミットしますよね。別に語りの分析がしたくて沖縄や部落に入るんじゃないんです。でも、沖縄で得られた語りを、沖縄という社会の現実や歴史や構造に結びつけると、差別・暴力だといわれる。ここで、私は何年も研究がとまってしまった。自分の博士論文を書きなおして『同化と他者化』を出版するまで、10年もかかりました。
ずっと書けなかったんですが、でもやっぱり、書かないといけないなと思った。それは、沖縄のひとのおかげなんです。「おまえは差別者だ」「基地を押しつけている側だろう」といったのも沖縄のひとですが、「ぜひ書いてください」といってくれたのも沖縄のひとです。そういうなかで私たちは仕事していく。自分の権力性とか暴力性に絶対に開きなおらずに、それを直視して、悩み倒して、それでも書く。
振り返ってみると、桜井厚の対話的構築主義は、若手の院生に罪悪感を植えつける構造になっているわけです。そして、自分の方法論を免罪符みたいにしていく。それを採用すれば倫理的な問題はクリアできるかのように。
現場に入って誠実に振る舞うのは、あたりまえの話です。現場について書くことで暴力をふるったとして、糾弾されることもある。調査先で迷惑かけることもある。私も何度もあります。それで反省するし、落ち込む。でも、それはみんなやるんです。そのなかで自分のポジションが問われてくる。それは特定の方法論のせいでもないし、別の何かの方法論を採用したからといってそこから免罪されるわけでもない。ただ僕は、これは桜井本人の責任だとは思いません。彼の理論を安易に自分の調査に当てはめて、それで方法論の問題をクリアしたみたいなことを言ってきた、周りの研究者の責任だと思います。
桜井厚を出発点にして、自分の調査の暴力性みたいなものと向き合わないといけない。向き合ったうえで、それを乗り越えて、どうやって社会について書くか必死で考えていかないといけない。社会学の存在意義って、そこでしょう。
――『現代思想』2015年7月号で書かれていた「鉤括弧を外すこと」という論文が、桜井厚批判への宣言のようなものですね。
そうですね。私はいま桜井厚を名指しで批判をしていますが、私は自分のことを勝手に、桜井厚の一番弟子だとも思っています。ほんとにそう思う。
ただやっぱり、彼が日本のエスノグラフィを30年くらい遅らせた面がある。豪快な、過激なエスノグラフィがもっと書かれたはずなのに、日本の社会学の質的調査のひとに罪悪感を植えつけて、手足を縛ってしまったんですね。
そのせいで、いま質的調査を使って書かれる社会学の本や論文が、「差別の現場に向き合ってまごまごする、わたしの誠実さ」みたいな話ばっかりになってしまった。読み手としては、その書き手がどう思うかはあんまり興味なくて、その現場がどうだったのかを書いてほしいわけです。
岸政彦インタビュー:次のページ