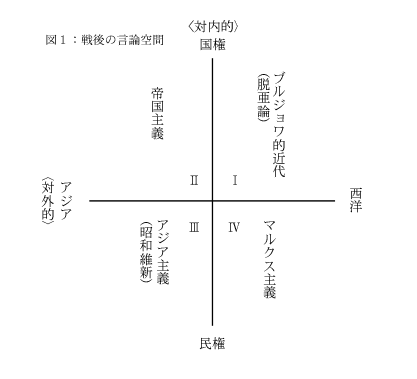第13回
第4章:日本と中国のあいだ
――「近代性」をめぐる考察(3)――
1. 「アジア的なもの」をめぐる言論空間
第13回
第4章:日本と中国のあいだ
――「近代性」をめぐる考察(3)――
1. 「アジア的なもの」をめぐる言論空間
前回に引き続き、もう少し柄谷行人の言論にこだわってみよう。欧米のポストモダン思想に近いところから出発したと考えられがちな柄谷だが、実はこれまでにも彼自身の「アジア」をめぐる問題群へのこだわりを感じさせるような仕事をいくつか発表してきている。特に彼の「アジアへのこだわり」が比較的前面に出ていると考えられるのが、昭和から平成に移り変わる節目の時期に発表された評論集『終焉をめぐって』である。
例えば、同書に収録されている「大江健三郎のアレゴリー」という文章の中で柄谷は、大江健三郎の代表作ともいえる小説『万延元年のフットボール』を題材にして、非常に興味深い指摘を行っている。その内容を簡単にまとめると、こんな感じだ。戦後民主主義を代表する「進歩派」知識人と見なされることの多い大江は、その社会問題に関する発言では一貫して西洋的・近代的な価値観を代表する者として振る舞ってきた。しかし、『万延元年-』のような小説の世界では、そのような近代的価値観と対立するような、暴力的で、謎めいていて、それで独特の力強さを持つ人物や世界を描いてきた。たとえば、『万延元年-』に登場する、転向した元左翼の活動家であり、「谷間の村」に住む人々の朝鮮人への反感を利用し、「天皇」と呼ばれる朝鮮人が経営するスーパー・マーケットに対する襲撃・略奪を煽動する主人公の弟・「鷹四たかし」という人物がその典型である。
柄谷は、大江の小説に登場する、西洋的近代とは対立する価値観を持つ人物は、多くの場合満洲や朝鮮半島といった「アジア」につながりを持っていることを指摘する。すなわち、大江の小説世界の魅力は、そのような西洋近代的な価値観の世界とアジア的な世界との緊張関係を寓話的に描くことで、近代以降の日本の思想的・政治的ダイナミズムを捉えている点にある、というわけだ。
さて柄谷は、以上のような大江の社会問題への発言と小説世界との「ねじれ」を、以下のような、対内的/対外的、および国権/民権という二つの軸により分けられる四つの思想的な立場の分類を用いて、以下のように表現している。
戦後の言論空間は、いわば右半分の第Ⅰ象限と第Ⅳ象限に閉じ込められている。左半分はタブーである、といってもよい。そして、一般に大江はこうした戦後の言説空間に忠実な旗手であるとみなされる。しかし、というより、それゆえに、小説において、彼は左半分にのみこだわっているというべきなのだ。『万延元年のフットボール』にかぎらず、語り手としての「僕」は、きまって第Ⅰ象限におかれている。「僕」は、戦後日本の状況そのものである。それは性的に不能で、非活動的で、自閉的である。そして、「僕」が怖れかつ惹きつけられる「弟」的人物は、いわば第Ⅲ象限にある。 注意すべきことは、この第Ⅲ象限が言語的でないということである。それは、いつも「なにごとか狂気めいた暗く恐ろしいもの」である。いいかえれば、「僕」が意識にあるならば、「弟」はエス(無意識)にある。そして、後者は言語化(意識化)されれば、しばしば第Ⅱ象限としてあらわれる。『終焉をめぐって』79~80ページ
たとえばⅣマルクス主義からⅢ亜細亜主義へ(保田與重郎)、Ⅲアジア主義からⅡ帝国主義への転向があった。あるいは、福沢諭吉が代表するように、ⅠからⅡへの転向もありふれている。(中略)実際は、このⅣ象限をぐるぐるまわっているのである。 恐らく今後もこの構造を免れることはできないだろう。戦後の"空間"は、いわば「アジア」を切り捨てた領域、つまり座標の右半分である。侵略であれ、解放であれ、「アジアに手を出すな」という禁止が、言説空間を支配している。実際には、戦前以上の経済的支配に至っているにもかかわらず、"意識"においてはそうなのだ。『終焉をめぐって』21ページ
おそらく、この見方は当時だけではなく、現状においても一定の妥当性を持つといってよいだろう。いや、こと言説空間に限ってみれば、事態はより後退しているといった方がよいかもしれない。例えば秘密情報保護法案の可決や集団的自衛権を認める憲法解釈の変更といった安部政権が推し進める政治状況について、いわゆるリベラルな言論人がしばしば政権に対する批判を表明している。だが、その多くは図の右半分に立脚して「かつての軍国主義的な道を歩もうとしている」自民党や政府の姿勢を批判するものであり、そこで自分自身が左半分の世界に「怖れ、かつ惹きつけられ」ている、という自覚が表明されることはほとんどないと言ってよい。
例えば、憲法九条の改正に反対する立場から時事問題への発言を積極的に行っている内田樹は、近著『街場の戦争論』の中で、戦後日本が安全保障や外交面でアメリカに従属的な姿勢に甘んじるほかなかった原因を、敗戦の経験が徹底的だったために、戦後の日本の政治に、戦前と戦後を架橋する「戦争主体」が不在になってしまったことに求めている(内田、2014)。その主張自体については取り立てて言うべきことはない。ただ問題は、内田が描く本来ならば戦前と戦後を架橋するべき連続性を持った(内田の言葉を借りるなら「強い現実」としての)日本もしくは日本人イメージからは、実際の戦前日本の歩みと切り離すことのできない「狂気めいた暗く恐ろしいもの」としての「アジア」との関わりがきれいさっぱり抜け落ちていることである。そのことを端的に表すのが、同書の中で彼が展開している「もしも1942年にミッドウェー海戦の後に日本が講和を求めていたら」日本は美しい「山河」を破壊されることもなく、戦前からの連続性に立つ主体性を維持したまま敗戦に臨めたはずだ、という思考実験であろう。だが、いうまでもなく1942年時点において日本の「山河」は破壊されていなかったかもしれないが、その軍隊は中国大陸への侵攻によって大量かつ残虐な殺戮をすでに繰り返していたのである。このアジアにおける日本の残虐行為も、内田にとって戦後に受け継がれるべきだった「強い現実」に含まれるのだろうか。
おそらくはこういった、「アジア的なもの」あるいは「アジア的なものとの苛烈な関わり」 に対する忘却のゆえに、彼(女)らの「リベラルな」「優等生的な」批判は、図の左半分の世界に大きく影響されつつ進行している事態に対して、ほとんど無力なままに終わってしまっているのではないだろうか*1。
さて、上記の大江健三郎の小説世界に対する評価には、柄谷自身の「アジア」に対する思想的態度も投影されていると考えてよいだろう。それを証明するかのように近年の柄谷は、以前にも増して「アジア的なもの」への関心を前面に出した言論活動を行っているように思われる*2。前回の連載 でとりあげた『帝国の構造』における中華帝国の統治に対する高い評価はその一つの現れである。だが、彼の「アジア的なもの」への関心という点ではもう一つ重要なものがある。それは、『遊動論』『柳田国男論』などの著作に現れた柳田国男へのまなざしがそれである。柄谷にとって柳田は、日本の「近代化され得ない部分(=アジア的なもの)」へのこだわりによって、いわば内在的な視点から日本の単線的な近代化=西洋化を批判し得た稀有な思想家、と位置付けられているのではないだろうか。
ここでは柳田の膨大な業績について論じている余裕はない。しかし、注目しておきたいのは、柄谷がその柳田論『遊動論』の中で、「日本資本主義論争」に言及し、そして次のような柳田の言葉を引用しながら当時の講座派=共産党の急進的な姿勢に対する批判的な姿勢を露わにしていることである。
現在の共産思想の討究不足、無茶で人ばかり苦しめてしかも実現の不可能であることを、主張するだけならばどれほど勇敢であってもよいが、そのためにこの国民が久遠の歳月にわたって、村で互いに助けてかろうじて活きて来た事実までを、ウソだと言わんと欲する態度を示すことは、良心も同情もない話である。柳田国男『都市と農村』。引用は『遊動論』18ページより
この言葉には、柳田の社会主義や左翼思想に対する批判というよりも、日本の農村に伝統的に受け継がれてきた「アジア的な」文化を「封建的遺制」として暴力的に切って捨ててきた、「講座派的」-あえてそう呼んでおこう―な姿勢に対する批判が込められているといってよい。そして明らかに柄谷も、柳田の当時はむしろ「反共」的あるいは「保守反動」的なものとして片づけられたであろう言説に、深い共感を示しているのである。それは、恐らくは、先ほど見たような大江健三郎論に仮託する形で現れた、柄谷自身の隠れた「アジア的なもの」へのこだわりと無関係ではあるまい。ただし、そこにみられる「アジア的なもの」は、大江健三郎論に託して述べられたような暗くて暴力的な存在ではなく、いわば、より優しく人々を包み込むような懐かしさを感じさせるものである*3。
まず、戦前・戦後を通じて日本共産党の主流を形成した講座派マルクス主義は、日本の現状を、「封建的な前近代性」の残存によって近代資本主義の普遍的な発展コースから逸脱したものと考え、資本主義の正常な発展とその先の社会主義革命を目指すために、まず日本社会に残る前近代性(封建遺制)の払拭を目指そうとする立場である。そして、このような「二段階革命論」に対抗する論陣を張ったのが労農派の論客であった。労農派の中には、向坂逸郎さきさかいつろうのように、むしろ日本社会にも普遍的な資本主義のロジックが貫徹することを主張し、資本主義の「歪み」を強調する講座派を批判する人々がいた。その一方で、猪俣津南雄いのまたつなおや櫛田民蔵くしだたみぞうのように、日本社会に唯物史観では割り切れない、いわば前近代的な要素が一定程度存在することを認め、それでも「近代化」は生じていることを説いた人々もいたのである。
このような日本にはたして近代的な資本主義が存在するのかどうか、という論争は、確かに後期資本主義国として台頭しつつあった戦前の日本においては切実な意味を持っていたであろう。一方、今日においてなおこの論争が注目に値するとしたら、その意義はどこにあるのだろうか。それはとりもなおさず、この論争に日本と「アジア」なかんずく中国との関係性およびその矛盾が凝縮されているからにほかならない。
そもそも、「日本資本主義論争」は、「後進地域たる(特殊性を持つ)日本において社会主義革命を実現させるとき、(マルクス主義の)「普遍性」をどの程度重視すればよいのか」という問題意識を掲げて行われたものであった。そして、1930年代後半から40年代にかけて、同じような問題意識を、中国の現実に当てはめて検討する議論が相次いで行われることになる。ただ重要な違いは、日本資本主義論争が「革命」のプロセスをめぐって争われたものであったのに対し、隣国中国を対象にして行われた論争は、日本の大陸侵略と分かちがたく結びついたものだったという点である。
その一つの例が、「支那統一化論争(以下、「統一化論争」)」である。これは、日中戦争前夜に、日本が「混乱しつつも統一化の方向に向かいつつある」中国にどう対峙たいじすべきか、という点をめぐって、いわば「三つ巴どもえ」ともいうべき思想的立場をめぐって行われた論争である(野沢編、1971)。
このうち第一の立場が、満鉄調査部に所属していた大上末広おおがみすえひろなどによって唱えられた、中国は「近代国家」成立後も依然として「半植民地」的な状態にあり、統一的な政権に支えられた資本主義的な発展は実現しない、という一種の「中国停滞論」である。
二番目の立場が、矢内原やないはら忠雄が1937年に発表した「支那問題の所在」に代表される、日中両政府の協調を説く議論である。矢内原は中国におけるナショナリズムの勃興と、それに支えられた統一化の機運を評価し、さらにそれが新興の民族資本(浙江せっこう財閥)と結びつくことにより、国民党政府の下での資本主義の発展を予想した。
そして三番目の立場が、尾崎秀実ほつみや中西功など、国際的な共産主義運動とのかかわりから中国における抗日ナショナリズムの高まり、中でも内陸農村部で支持基盤を拡大しつつあった共産党の動向に注目した人々による議論である。彼らは、矢内原らの「日支提携論」を、それが資本家の利益を追求したものに過ぎないと一蹴いっしゅうする一方で、帝国主義勢力による中国の半植民地化、従属化を主張する議論に対しても、労働者・農民などによる下からの大衆運動(=民族戦線)による統一化の契機を見ていない、として厳しい批判を行った。
ここで注意したいのは、この論争は、中国の「資本主義的発展」がどの程度普遍的な性格をもつのか、という点をめぐる意見の対立を背景とした、いわば日本資本主義論争の対中国バージョンという性格を持っていた点である。
例えば、矢内原のいわば「中国近代化論」を否定し、その前近代性、従属性を強調した大上は、講座派の理論に忠実な論客として、いわば講座派の理論的枠組みを満洲や中国大陸の分析に適用することで当時の論壇で評価を得ていた(福本、2000)。中国において近代的な国家や資本主義的な発展は成立しえない、という大上の議論は、蒋介石を首班とする南京国民政府は相対的な軍事的優位によって「中央政府」の体裁を整えているだけで対等な交渉相手ではない、という当時の政府・軍部の対中強硬派の姿勢を補完する役割を持っていた。言うまでもなく、実際の日本の大陸政策は近衛内閣の「国民政府を対手あいてとせず」という声明(1938年)に代表されるように、南京政府を軽視しつつ自らの権益の拡大を図る、という路線のもとに進み、ついには泥沼の全面戦争へと突き進んでいくことになる。当時、大上のようにマルクス主義を信奉しつつ、結果として日本の中国侵略を補完するような役割を果たした知識人は決して少なくなかった。講座派の論客として出発し、その後転向して大アジア主義のイデオローグとなり、戦後は共産党員として日中友好を唱えた平野義太郎はその代表的なケースである。
すでに述べたように、講座派の理論は日本の「後進性」を強調し、まず「近代化のための革命」が必要であることを説く。同じ論法を中国に適用すれば、蒋介石政権の「前近代性」を強調することになるのは理の当然であったのである。これらの例が示唆するのは、もともと日本社会と西洋的な近代社会との異質性にこだわる講座派的な視点が、「アジア」という西洋以外の他者に対して向けられるとき、容易に帝国主義的な侵略の思想に転化してしまう、ということである。
恐らく、柄谷が柳田国男を援用しながら改めて講座派(的なるもの)に厳しい批判を投げかけたのは、そのような「前近代性」をアジアに対して見出してきた、戦前・戦後の日本における言論の暴力性を批判するという意図があってのことだと思われる。この延長線上に、彼の『帝国の構造』における中国の前近代における帝国的秩序への肯定を置いてみると、その構図は明らかであろう。柄谷にとって柳田は、「農村における前近代的な協働のあり方を否定的な媒介にして、新たな共同性を創造しようとしてきた」存在であり、それゆえに近代的な「資本=ネーション=国家」の論理を批判するのに重要な思想家として再評価されることになる。
ただし、あくまでも日本一国内の問題について論じた柳田の思想からは、近代国民国家を相対化するような国際秩序のあり方のヒントを得ることはできない。そこで柄谷は、それを補完するために、「前近代的な国際秩序のあり方を否定的な媒介にして、新しい国際秩序を創造しようとする」ロジックを、前近代中国における帝国的統治のあり方に見出そうとしている、というのがさしあたっての僕の見方である。
しかし、この二つの「前近代的なもの」、すなわち柳田が論じた日本の伝統的な農村の文化と、前近代中国における帝国的秩序を同じ次元で評価することには明らかな無理がある、と言わざるを得ない。柳田が目を向けたのはあくまでも権力とは無縁の常民であり、あるいはマイノリティとしての山人であった。「前近代的なもの」がそのようなものである限り、現代の市民社会に生きるマジョリティとしての日本人が、マイノリティを包摂した「新たな共同性」の基盤としてその精神を活かしていくことは可能だろう。
一方、同じ「前近代的なもの」の再評価と言っても、あくまでも権力あるいは統治の立場から、前近代中国における帝国的秩序を評価することは、それとはまったく異なる意味を持つと言わざるを得ない。なぜなら、「帝国」的な、すなわち国家への対抗勢力を欠いた「単一権力」の下での統治は、そもそも権力の「分有」を前提とし、国家にアカウンタビリティを要求する市民社会のロジックとは相容れないからである。相容れない以上、市民社会のロジックと矛盾を来さない形で、帝国的な秩序が「高次に復活」することもまたあり得ない、と言うべきである。それがあたかも将来においてあり得るかのように語ることは、アジアにおいてこれまで近代性(モダニティ)の実現を希求した多くの人々が、「単一権力」の下での暴力にあらがうために多くの血を流してきたし、現在でもまた血が流され続けている、という事実を忘却してしまうことにつながりかねない。
このように考えると、柄谷の帝国再評価の議論は、欧米とは異なる発展のコースを辿ってきたアジア諸国-なかんずく中国・朝鮮半島-に対する一種の寛容な姿勢を貫こうとするあまり、ともすれば普遍的な評価の基準を見失ってしまいがちだった、戦後革新勢力によるアジア論の轍てつをそのまま踏んでいるといわざるを得ないだろう。そこに欠けているのは、民衆と権力との関係性に関する根源的な考察である。
本連載をまとめた書籍が刊行。好評発売中です。
-

- 日本と中国、「脱近代」の誘惑 ──アジア的なものを再考する
-
梶谷懐
発売:2015年6月6日 - Amazonで購入
- お試し読み