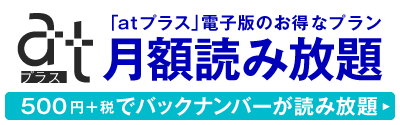──岸政彦さんは社会学者であり、沖縄や被差別部落でのフィールドワークを長年続けています。戦後沖縄の本土就職者をテーマにした『同化と他者化』(ナカニシヤ出版、2013年)を初めての単行本として出されたあと、さまざまなひとの語りを集めた『街の人生』(勁草書房、2014年)、「分析できないもの」を集めたエッセイ集『断片的なものの社会学』(朝日出版社、2015年)と、著作を次々と刊行されています。
一連の著作はとてもインパクトがあって、「生活史」という言葉をよく耳にするようになりました。そこで今号の『atプラス』では、岸さんの協力のもと「生活史」をテーマとした特集をくむことにしました。まず、生活史とはどういうものかご説明いただけますか。
生活史とは
岸 生活史は、ライフヒストリー、ライフストーリー、オーラルヒストリーなどと呼ばれることもありますが、社会学における質的調査のひとつで、個人の生い立ちや人生の語りを聞いて社会について考える調査法、あるいはそこで聞かれた語りそのものを指します。他の領域では食器や衣類などの日常的な生活文化の歴史や、あるいはもっと(ライフヒストリーという言葉で)「生命・生物の進化史」みたいなものを指すこともあるようですが、社会学ではおもに個人の生い立ちの語りの意味で使われています。
欧米の社会学では、ライフヒストリーはいまでは伝記とか生い立ちぐらいの意味になっていて、あまり使われる言葉ではないんです。ライフストーリーという言い方も同じように、ほとんど伝記とか自伝っていう意味になってます。あとそれから、ナラティブという言い方もありますが、それは「物語研究」の分野で使われることが多いかもしれません。それは文学研究の一部で、いろいろなところで語られる物語構造みたいなものを考えていくものです。
個人の人生から社会を語ることは、ライフヒストリーっていう言葉を使うよりも、単に「インタビュー」っていいます。インタビューは、参与観察と区別するわけではなくて、質的調査法のよくある方法のひとつになっています。とりたててライフストーリーといわないような気がします。インタビューで得られた生い立ちや人生の物語はバイオグラフィーといわれます。
むしろ、歴史学におけるオーラルヒストリーという言い方が一般的になっています。欧米の社会科学や人文学で個人の生活史をさして使われるのはこの言葉ですね。オーラルヒストリーという言葉はもちろん社会学でも使いますが、どちらかといえば歴史学をやっているひとたちが使います。文書資料中心主義、あるいは「偉人伝」や大規模な事件史を中心とする従来の歴史学に対する批判という側面もあるんです。語り手が現存する近現代史に限って、歴史的な事件やできごとを体験した当事者の証言を聞くものです。
徐々にですが、文書中心の偉人伝みたいな「大文字の歴史学」ではなくて、無名の市民が社会とどう関わって、大きな歴史的なプロセスをどう体験したかという歴史学が力をもつようになっています。文書中心主義から口述されたデータへ、偉大なひとから一般のひとへというふたつの流れがあるわけです。
以上のように、学問的な源流はいろいろちがいますが、ライフヒストリー、ライフストーリー、オーラルヒストリーという手法やデータに、大きなちがいがあるわけではありません。私は日本語の「生活史」という言葉が好きで、愛着があるので、一括してこれを使うようにしています。
日本の生活史のはじまり
シカゴ学派のトマスとズナニエツキによる『ヨーロッパとアメリカにおけるポーランド農民』(1918-20)が生活史調査の嚆矢ともいわれます。ただ、個人の語りだけを使っているわけではないので、この本のデータは、生活史というより「生活記録」「ライフドキュメント」と呼ばれます。トマスとズナニエツキは、20世紀のはじめに貧しいポーランドからアメリカにやってきた農民たちの態度や規範が、シカゴという大都市で暮らすうちにどのように変化していったかを探ろうとしたのですが、そういう調査をやろうと思っても母集団もわかんないし、統計もとれないので、新聞記事とか手紙とか手記とか裁判記録とかのデータを、手に入るだけぜんぶ集めたんですね。ありとあらゆる記録を集めて、総合的に分析しようとしたんです。これが社会学における質的調査のはじまりであり、またその代表作といわれています。このあと、シカゴ大学の社会学部からは、都市のスラムや貧困という問題に立ち向かった、ジャーナリスティックな社会学者がたくさん輩出されます。いくつかは翻訳されていて、日本語で読むこともできます。
質的調査は日本でもおこなわれてきましたが、特に生活史のおもしろさを日本で定着させたのは、社会学者の中野卓(なかのたかし)なんです。彼は生活史の研究をする前に、『商家同族団の研究――暖簾をめぐる家と家連合の研究』という有名な本を書いています。中野卓の師匠は、有賀喜左衛門という日本の民俗学と社会学の偉いひとで、日本の農村の家族の研究をしていました。
中野卓がわりと年をとってから出した『口述の生活史――或る女の愛と呪いの日本近代』(御茶ノ水書房、1977年)は、ものすごいインパクトがあったんです。日本の生活史はそこからはじまるといってもいいと思います。このあたりがいわば、日本の社会学における生活史研究の「第1期」ですね。ここから日本の生活史は、独自の発展を遂げているんです。私は、日本の生活史研究はわりとおもしろいと思います。翻訳されて広がっていけばいいなあと思います。
『口述の生活史』は「奥のオバァサン」という方の記録です。中野卓が水島コンビナートにチームで調査に行ってたときに、このおばあさんとたまたま会うんですよ。彼女のことを、中野が個人的におもしろいと思って、調査が終わったあと、テープレコーダーをもって通うんですね。東京から倉敷の水島コンビナートまで。
「奥のオバァサン」は、戦争中に満州とか朝鮮に行っていたひとで、ちょっとシャーマンぽい、エキセントリックなおばあちゃんです。その語りをテープにとって、語り口を残したままほとんど編集しないで本にしたんですね。「中野卓編著」というかたちで。「編著」にしたのは、彼女がもうひとりの著者だっていう思いがあったのでしょう。
この本のおもしろさは3つあります。ひとつは、日本の土着的な信仰とか農村の貧しさとかがどういうものであったかということ。ふたつめが、一般の庶民が戦争にどう翻弄されたかということ。3つめ、私はこれがいちばん重要なことだと思ってるんですが、水島コンビナートの近くの村で話を聞いたことです。
いちど、グーグルマップで「奥のオバァサン」が住んでた村のあたりを検索してみたことがあります。山と海にはさまれた、ものすごくひなびた漁村なんですけど、すぐ隣に巨大なコンビナートがあるんです。こういうところで、日本の土俗的で土着的な、マジックリアリズムの小説みたいな話を聞くっていうことが、中野卓にとってどういう経験だったんだろう。
彼は、東京から何回も彼女の家に通うわけです。1~2時間、満州の話とか、狐憑きの話を聞いたあとで、その家を出て見上げると、近代的な工場群が目に入ったはずなんです。そこで、あの本をあのかたちで出そうと思ったんじゃないか。これがまさに、いまの日本の姿だと。国家とか経済とか資本主義とか近代とかいったものぜんぶが、おばあさんの前近代的で土俗的な語りのなかに入っている。
ただ、そのへんの対比をそこまで描いているわけではないですが。私の勝手な想像ですけどね、個人の生活にすべてが入ってるんだというのを、おばあさんの家を出て、目の前に広がるコンビナートを見上げたときに、実感したんじゃないかと思う。こんな話は誰もいってないですけどね。
ただ、さっきほとんど編集しないで出したといいましたけど、わりと編集してますよね(笑)。
――中野さんの説明もそれなりに入ってます。
文末がぜんぶ小文字のカタカナなんですよ。「でしョ」とか「なァ」とか。こういう表現って、60~70年代の表記法なんですよ。勝手な思い込みなんですけど、団塊の世代が、ちょっとくだけた文章を書くときに、語尾が小文字になったりすることがある(笑)。私からすると、すごい古くさい。
――いま読むと、ちょっと読みづらいなと思いました。
いちど『口述の生活史』を書き写して、カタカナをひらがなに変換したことがあるんですよ。格段に読みやすくなりました(笑)。そういう、ある時代の編集の刻印はされていますが、偉大な本だと思います。
岸政彦インタビュー:次のページ