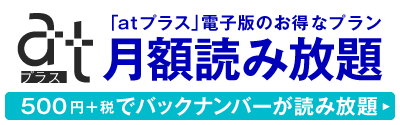生活史のいま
いま生活史は第3期に入ってると思います。さきにいったように、第1期が中野卓、第2期が桜井厚と谷富夫です。これからはもういちど実証的な生活史、あるいは歴史社会学的なオーソドックスなオーラルヒストリーが注目されると思います。ただ、いまの若手や中堅で、実証的な生活史に特化しているひとはそんなにたくさんいるわけじゃない。今回の特集の執筆者でいえば、私と齋藤直子と朴沙羅くらい。もちろん今回の執筆者以外で実証的な生活史をやっているひとは何人かいますけど。
――今回の特集は、生活史を盛り上げたいという意図があるんですか。
そう。ほかの執筆者の方は生活史じゃなくて、エスノグラファーです。だけど今回は、語りを使ってくださいといってます。あえてそうすることで、生活史のおもしろさや「やりがい」みたいなものが浮き彫りになればいいなと。そして、これを読んだひとに、自分でもやってみようと思ってもらえたらいいですね。
――生活史とエスノグラフィのちがいはなんですか。
語りをそのまま引用するかどうか、ですね。現場で起こったことを小説風に書くか(エスノグラフィ)、録音した語りをそのまま使うか(生活史)。語りそのものに対するフェティシズムというのは、生活史の本質的なところです。それがデータとしてどういう意味があるのか、それがエスノグラフィックなデータとどうちがうのかっていうのは、すでにたくさん議論されてますけども、まだまだこれからの課題です。
個人的な感触としては、語りがいちばんおもしろい。『街の人生』もそうです。スタッズ・ターケルの影響でつくったんです。高校生のときにターケルの本に出会って、夢中で読みました。いつかこんな本を書きたいと思った。ひとの人生の語りって、そのままで十分おもしろいと。そこからどうやって社会の分析を組み立てていくかというのが、今後の課題です。
他者の合理性を理解する
生活史から社会について語るって、社会学の理論からいえば、「行為論」の枠組みのなかに入ります。いま、マックス・ウェーバー、アルフレッド・シュッツ、タルコット・パーソンズ、ピエール・ブルデューを読みなおそうと思ってます。私がいちばん影響を受けてるのはブルデューですが、社会学の行為論をもういちど勉強したいです。
構築主義とはようするに、相互作用論なんです。現場の相互作用が「主語」になるんですね。対話的構築主義もそうで、インタビューの聞き手と語り手の対話が主語になっているわけ。そうすると、述語もそれに従う。「ここでのこの会話は」というのが主語になるから、述語も「こういう意味のやりとりである」というものになる。これは会話に対する意味づけです。だから、個人の生活史と論理的にズレるというか、かなり水準がちがうことになる。
個人の生活史を使おうとしたら、語り手を主語にしないといけないでしょう。そうすると、述語に来るのが、行為の類型なんですよ。主語に語り手あるいはその語りや行為や記憶をもってくると、述語は行為類型になる。語り手はそのときこういう行為をした。その行為はこういう意味だ、と。それはどういう行為かを類型化してるんですね。あるいは「理解」している。
いま私は、「他者の合理性の理解社会学」というテーマでいろいろ勉強してます。特に、一見不合理に見える行為が、当事者にとってどのような「意味」があるかということを考えています。社会学のほかにも、そういう「不合理な行為の合理性」に関する研究はいろいろあります。行動経済学の「双曲割引」や、分析哲学における「アクラシア」(不合理性)の研究などは、とても勉強になります。もちろん、私なんかただのつまみ食いで、私の能力ではちゃんとした経済学や哲学の議論はとてもできませんが、それでも何かのヒントが得られるかもしれないと思って勉強させてもらってます。
そもそも、ポール・ウィリスの『ハマータウンの野郎ども』のようなエスノグラフィが描いてきたのがまさにそれ、一見不合理な行動をどうしてとってしまうのかという話です。ウィリスが70年代に参与観察したイギリスの労働者階級の少年たちは、学校で自らドロップアウトして不良少年になることで、結局は自分の階層的上昇のチャンスを自らつぶしてしまう。学校で我慢して勉強すれば上にあがれるのに、教室でグレることのほうが快楽だからグレるんですね。それでいまは楽しくなるけど、結局、親と同じような労働者階級になってしまう、という話です。文化的再生産論っていいます。
丸山里美さんの『女性ホームレスとして生きる』のなかでも、女性のホームレスがせっかく生活保護もらってアパートに入ったとしても、付き合ってるホームレスのいる公園に帰ってきてしまうという話があります。丸山さんがじっくりインタビューすると、「そうだよね、帰ってきてしまうよね」と、わかってくるんです。こういう状況だとひとはこうするんだ、ということを集めるのがひとつの質的調査の社会学です。
私が強く思うのは、それぞれの質的調査が孤立しているわけではなくて、結果としてみんなで「人間に関する理論」を積み重ねていってるんじゃないかっていうことです。この「人間に関する理論」をつくっていく作業を、それぞれの現場でばらばらにやっている。なかなか連携するのも難しいのですが、経済学や哲学なんかのほかの領域とも結びついていけるはずです。社会学、経済学、哲学のそれぞれの一部が集まって、広い意味での合理性に関する「人間学」みたいになればいい。
ウェーバーが『理解社会学のカテゴリー』の冒頭で「人間の行動はいろいろな関係や規則性をもっていて、それは理解可能なかたちで解明しうる」ということをいっていますが、それは、人びとの行為が合理的であるということです。結局、生活史が語りを聞いて書くことをつうじてやっているのは、人びとの行為の「再合理化」なんですね。
――つまり、他者の行為にある合理性を記述するということですね。
そう。合理性といってしまうと、なんか冷たいかんじがしますが(笑)。ウェーバーへの批判もそうでしょう。「行為の合理性を理解する」といったときに、行為は合理的なものではない。もっと人間的な何かなんだ、と。合理性っていうと、金勘定とか計算みたいに思うでしょう。でも「実践的な合理性」っていうのは、ときとして自分にとって損になるようなことも含まれるんです。基本的には、ある行為者がある行為をした場合には、ほとんど必ずなんらかの理由や動機があるはずだと思っています。理由や動機があるということは、それはその行為は合理的であるということです。ただ、その合理性が、外からだと見えにくい。だから私たちにはわからない合理性にもとづいて行為しているひとを、ついつい非合理的だとか、あるいは「愚かだ」とかいってしまうんです。あるいは「自己責任だ」とか。でも、その裏側にある、そのひとなりの合理性を、社会調査をつうじて明らかにして、そしてそれをみんなにわかるように記述していく。これが質的社会学の仕事のひとつだと思っています。
行為責任を解除する
ここ2年くらいで書いてるのは、じつは全体としてみればひとつのプロジェクトで、いまいったことをひとつずつ取り出して書いています。「語りはおおまかに事実だ」というのが『現代思想』で書いた「鉤括弧を外すこと」ですね。シノドスで書いた「爆音のもとで暮らす──沖縄・普天間における「選択」と「責任」」は、「自分で選択した行為でも、その責任をすべて負わなければならないわけではない」という話。私は、それが質的調査の社会学の存在意義なんだと思います。
他者の合理性を再記述する、つまり、行為の合理性を理解するとどうなるか。その帰結はいろいろあると思いますが、そのひとつは、行為責任の解除です。「そういう状況なら、そういうことするのも仕方ないな」というのが理解でしょう。
私たちは、ついついマイノリティや社会的弱者、あるいは「他者」の行為に対して、「自己責任」という言葉で、その責任を帰属させてしまいます。私はこれは、大げさにいえば、社会のつながりそのものを解体することになると思っています。もういちど私たち社会の連帯を取り戻そうとすると、まずはマイノリティや社会的弱者の生活がどういうものであるか、そこでどういう行為がどのような理由や根拠で選択されているかを理解する必要があるんです。「そういう状況なら、そういうことするのも仕方ない」というような話をたくさん書いていくしかない。もちろん、どの対象にもこれができるわけではないですし、書くこと自体がもつ「暴力性」のような問題もありますが……。
質的社会学の目的があるとすると、それは人間として当然の行為なんだ、ということを、生活史やエスノグラフィの記述によって、人びとに理解してもらうということです。この「理解」がもつ意味を、もうすぐ出る有斐閣の北田暁大さんとの対談本のなかでは、「隣人効果」と呼びました。私たちは、調査対象の当事者になりかわったり、その人生を「直接」理解することはできない。でも、「そういう状況なら、そういうことするのも仕方ない」という記述を重ねることで、私たちは当事者の「横に黙って立つ」ことはできるかもしれない。私たちは当事者そのものになることはできませんが、その隣人になら、なることはできるかもしれないのです。
今号の特集について
今号の特集について、編集長の柴山さんから相談があったのは年末ぐらいだったでしょうか。生活史について書いてくださいといわれて、私は急遽、普段から尊敬している若手のフィールドワーカーたちに依頼して、生活史の語りを使って自由に書いてくださいとお願いしました。みなさんご快諾くださって、今回の特集になりました。みなさん、すばらしい原稿を書いてくださいました。詳しくは本誌をご覧いただくとして、いま日本の社会学が大きく方向転換しようとしていることが伝わったらいいなと思います。
私は、日本の社会学も、炎上芸人みたいな「おもしろサブカル批評」や「上から目線の万能知識人による社会評論」から、ちゃんと現場に入り込んで社会問題を地道に調査をする、「あたりまえの学問」になってほしいと思います。もちろん実際には、「あたりまえの社会学者の仕事」をしているひとのほうがはるかに多いのですが、ここはこれまであまり注目されませんでした。今号の特集には入らなかった若手の社会学者もたくさんいますし、これから社会学もどんどん変わっていくと思います。この特集がそのきっかけのひとつになれば幸いです。