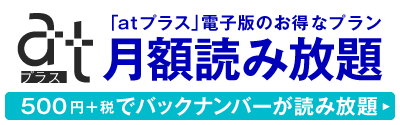『青年と学問』を読む/柳田國男と日本国憲法
民俗学者として一般に知られる柳田國男は、その晩年である1960年5月、公的な場(といってもそれは彼が多感な少年期を過ごした村からそう遠くない場所での小さな集まりだった)で「日本民俗学の退廃を悲しむ」と題する講演をおこなったとされている。柳田の「最終講演」として語られるものである。実際にはこの後も小さな集まりで話をした記録は残っているが、その題名から柳田の遺言のように受け止められてきた。
死の二年前のことである。死後、柳田が残した本物の「遺言」には彼の学問については何も語られていなかったとされる。
柳田はその晩年、彼の創り上げた学問が彼の望んだのとは違う形になってしまったことに、憤っていたといわれる。あらためて、そのことが伝わってくる題名である。聴衆の一人・菱田忠義によってノートがとられ、後に、柳田のいささかかわった弟子であった千葉徳爾によって公開されている。それを読むと、興奮して声もかすれ、という印象だったようだ。
その最後の方にこう柳田はいった、とメモにあるという。
憲法の芽を生さなければいけない
※菱田忠義のノートより(千葉徳爾「柳田國男の最終公開講演『日本民俗学の退廃を悲しむ』について」『日本民俗学194号』1993年、日本民俗学会)
民俗学者・柳田國男の公の場での、彼の学問への「遺言」がこのように結ばれていることにまず驚いてほしい。
日本の民俗学は1980年代には、「落日」と揶揄され、実際、妖怪研究の代名詞となり、アニメやラノベの「妖怪」キャラクターのソースとさえ化している。正直にいって学問としての進歩は止まった感がある。
一方では、柳田にたいしては、近代化の過程で失われていく民間伝承などの伝統文化を記録保全しようとした伝統主義者だとみなす、表面的な理解がある。それも彼の学問の正しい理解だとは言い難い。
柳田國男のこの「憲法」についての最後の呟きは、柳田なり、彼の学問のパブリックイメージとは全く一致しないだろう。今の人々は、この一節を持って、あるいは柳田をありふれた戦後民主主義、「サヨク」だと穿った見方さえするかもしれない。しかし柳田は明治国家の官僚であり、貴族院書記局長として大正天皇の即位礼をとり仕切った人物である。柳田の思想を天皇制や植民地支配の「補完」的思想とみなす批判も少なからずあった。
いずれにせよ、柳田國男という人とその学問は、気がつけばひどく見えにくくなっている。
では、柳田は何故「憲法」について遺言の如く呟いたのか。
一つには柳田國男が「日本国憲法」の成立に枢密院顧問官としてその審議に関わっていたという歴史的事実と関わりがある。
枢密院は、明治憲法制定時にその草案審議のために創設された。明治憲法下に於いては天皇の最高諮問機関と位置付けられている。そして柳田は敗戦の翌年、1946年、いわば最後の枢密院顧問官の一人として任じられ、戦後憲法、すなわち「日本国憲法」の草案の審議に関わっているのである。その審議は形式上に近いものと従来されてきて、柳田の発言は公文書上には残っていない。
しかし、明治憲法下の制度の中で戦後憲法の成立に立ち会ったことは少なくとも柳田國男という人にとって「形式上」に留まるものではなかった。
「憲法の芽を生やさねばならない」という遺言の如き呟きは、最後の枢密院顧問としての責任に柳田が最後まで貫かれていたことを物語っている。
それにしても柳田が何故、かくも「憲法」に拘ったのか。
それは単に戦後憲法の成立にただ立ち合った、ということには留まらない。むしろ、戦後憲法の中にあった思想は、戦前に柳田國男という人の中にあったのである。
そのことを理解する手懸かりを私たちは『青年と学問』(1928年)に見ることができるだろう。
今回は柳田國男と日本国憲法の関わりを考えるために、同書の中から1925年に長野県下でおこなわれた講演がベースとなった表題作の「青年と学問」の冒頭部分を読んでいこうと思う。
同書は1928年に刊行し、1931年に再版している。柳田はこの少し後、『郷土生活の研究法』(1935年)、『民間伝承論』(1934年)といった、未だ「民俗学」と自ら呼ぶことに躊躇としていた彼の学問の方法論上の入門書を続けて上梓する。『青年と学問』もその一冊と見なされることが多く、事実、「再版に際して」という一文には、同書は「郷土研究に関しての、私の論述」「研究者の間に、汎く読まれて欲しい」とある。
しかし、この「青年と学問」の中で語られる内容を見た時、彼の晩年の「呟き」の意味が確実に見えてくる。
そこで語られていることは、驚くべきことに戦後憲法と通底しているのである。その意味を今回は、歴史的背景を踏まえながら読み取って行く。その作業を通じて、日本国憲法が占領軍によって押しつけられたものではなく、その思想の中核、特に憲法前文や9条に見られる考え方は「戦前」の柳田の中にあった、と理解できるはずだ。
それでは、始めよう。
まず、冒頭のこの一節「最近に諸君と会談してから、はやすでに三年あまりを過ぎた。あの後日本にはいろいろの事が起り、好(よ)い事もあったが好くない事の方が多かった」というくだりだが、「青年と学問」の講演は1925年5月だから、「いろいろの事」の中心にあるのが、1923年の関東大震災であることは言うまでもない。柳田國男は関東大震災の報を聞くと、ジュネーブの国際連盟の委員としての職を辞し、日本に帰国する。そして朝日新聞編集局顧問として同紙に、普通選挙施行の社説を立て続けに書き、大正デモクラシーに合流したのである。
そもそも、1919年、明治国家の官僚を辞した直後は、朝日新聞の客員として日本列島を南下し、沖縄、台湾、インドネシア辺りまで下る旅を目論んでいた。しかし、沖縄に辿りついたところで、いささか強引に国連の委員に任じられるのだ。「南」への旅は「日本人の起源への関心」というロマン主義的な関心に基づくもので、柳田の学問には一つにはこういう側面がある。一般の人々が考える民俗学とは柳田の学問のこのようなロマン主義的側面をいうが、ぼくが今回、君たちと読みとっていきたいのはそうではない、もう一つの彼の学問の側面である。
柳田にとって震災が、彼の大きな転換点であったことは以下の記述から伺える。
大正十二年九月一日の関東大震災のことはロンドンで聞いた。すぐ帰ろうとしたが、なかなか船が得られない。やっと十月末か十一月初めに、小さな船をつかまえて、押しせまった暮に横浜に帰ってきた。ひどく破壊せられている状態をみて、こんなことはしておられないという気持になり、早速こちらから運動をおこし、本筋の学問のために起つという決心をした。
(柳田國男「官界に入って」『故郷七十年』1974年、朝日新聞社)
柳田は関東大震災の報に触れて、再び「社会」に目覚める。ここで「本筋の学問」と言っていることこそ「青年と学問」で説くことになる彼の学問だ。南洋に向かった学問は「本筋」ではないと認めているのである。「運動」という言い方にも注意しておこう。彼の学問は、社会運動としての側面がある。それが、妖怪研究とは違う、もう一つの民俗学である。
さて、再び、と記したのは、いずれそれについての柳田の文章を読んでもらうが、彼は幾度か彼の学問を、社会を良くするための社会運動としてつくろうとして頓挫しているからだ。「南」へと、一度、彼が向かいかけたのは、柳田がしばしば見せる現実逃避である。そういう弱さをもこの人にはある。
しかし、彼は今度こそ本腰を入れて自分の学問をつくろうと考えた。そのことは立て続けに3つの入門書を出版したことからもわかる。中でも柳田のこの書は「震災後の思想」だといえる。
つまり彼がこの「青年と学問」の中で説こうとしているのは、一つには「震災後の学問」のあり方だといえる。そのことは、まさに、震災後としての現在において君たちがどう学んで行くかという問題と重なりあって来る。
ぼくが、まず、君たちとこの本を読み始めたいのはそれ故だ。
では、それは柳田のいう「本筋の学問」とは、どういう学問か。以下のくだりを読んでほしい。
学問なんか何のためにするかという質問は、じつはもと我々には不愉快なる軽蔑(けいべつ)の言葉に聴えた。
今でもそうだが、学者たちは、学問は何のためにするかという質問を嫌う。しかし、そういう人たちは学問とは「塵(ちり)の浮世(うきよ)の厭(いと)わしいゆえに、しばしはこれを紛(まぎ)れ忘れようとするような、高踏派(こうとうは)の上品な娯楽(ごらく)」、つまり現実逃避の手段としていたり、上流階級に向けて知識を切り売りする人々であって、学問とはそのようなものであってはならないと信じたい、と柳田は、青年たちに学問の理想を説く。学問が「眼前に痛切なる同胞多数の生活苦の救解」、つまり社会の人々の諸問題と何の関わりを持ち得ないのは自分には不満だと言い、柳田は社会に「応用」する、つまり社会に役に立つ学問が必要だというのである。
大塚英志寄稿:次のページ