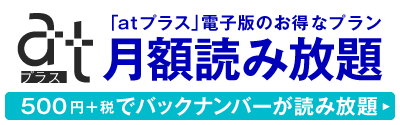実は『青年と学問』と不戦条約の関係については、一度、角川書店の原稿で触れたことがあった。すると「青年と学問」講演は1925年であり、柳田は1928年の不戦条約の内容を知るはずがない、という校閲が入った。この何年かしばしばこういう「政治的」な校閲が角川でも他所の出版社でも入る。「左派」的と取られる記述にのみ、校閲がはいる。しかし、柳田は既に記したように、第一次大戦後、1921年に国際連盟委任政治委員となり、北米やヨーロッパを回り、22年にジュネーブの国連に滞在している。つまり、不戦条約に向けた国際的な機運やその裏側の思惑も知り得る立場にあったことは明白である。昔の校閲なら、そこまで調べたが、いまはWikipediaで、表面的な事実をさらうだけだ。
言うまでもなく、この不戦条約は一方では戦後憲法の前文や9条の前提となっている。そのことは、戦後憲法を考えるうえで、大前提である。
柄谷行人は『憲法の無意識』の中で「憲法九条は戦争を違法化したパリ不戦条約(一九二八年)に淵源する」という言い方をし、更に不戦条約はカントの「永遠平和」という理念に基づいているという。より、普遍的な思想なのだ、と柄谷は言いたいのだろう。
柳田がカントの「永遠平和」論を踏まえていたかは、ぼくにはわからないが、重要なのは憲法前文や9条と同じ考え方は、戦前に於ける「個人道徳」の可能性として柳田によって説かれた「戦前の思想」と、まさに柳田という人を介して連続しているということだ。「憲法9条」や「前文」は「戦後の思想」ではなく「戦前の思想」なのだ、ということを君たちには理解してほしい。
さて、その時、柳田が「青年と学問」の中で「国民自身」が国際間の問題を戦争以外の手段で考える当事者でなくてはいけないと考えていたことにもう一度、注意を促したい。彼は、何故、国家による不戦の前提に国民を置こうとしたのか。
パリ不戦条約一条にはこうある。
第一條 締約國ハ國際紛爭解決ノ爲戰爭ニ訴フルコトヲ非トシ且其ノ相互關係ニ於テ國家ノ政策ノ手段トシテノ戰爭ヲ抛棄スルコトヲ其ノ各自ノ人民ノ名ニ於テ嚴肅ニ宣言ス
憲法9条の条文と酷似している。この条約を日本は戦前、批准しているのである。
しかし、批准にあたって一悶着あり、以下のような付帯条件とともに、批准が行なわれた。
帝國政府ハ千九百二十八年八月二十七日巴里ニ於テ署名セラレタル戰爭抛棄ニ關スル條約第一條中ノ「其ノ各自ノ人民ノ名ニ於テ」ナル字句ハ帝國憲法ノ條章ヨリ觀テ日本國ニ限リ適用ナキモノト了解スルコトヲ宣言ス
日本は、「人民ノ名ニ於テ」、つまり、国民の意思によって「國家ノ政策ノ手段トシテノ戰爭ヲ抛棄スルコト」を宣言するのを拒否したのである。
これが「不戦条約中「人民ノ名ニ於テ」の問題」とされる事件である。
「人民ノ名ニ於テ」という一句が、明治憲法の規定する天皇の統治大権に抵触する、即ち「国体毀損の虞れ」があるという批判が当時巻き起こり、この一節のみ、日本にはこの条約は適用されないと宣言した上で、日本政府はようやく、不戦条約を批准したのである。
そして注意すべきは、「人民ノ名ニ於テ」への批判の中心の一つが枢密院にあったことは多くの歴史資料が示しているところである。
「青年と学問」講演の時点では、柳田はさすがに「人民ノ名ニ於テ」が枢密院によって政治問題化され削除されようとすることまでは予見できようはずもない。
しかし「個人道徳」と「普選(普通選挙)」と柳田が言う時、その主張は「人民ノ名ニ於テ」という文句と一致することは明らかだ。つまり不戦条約という第一大戦後の「世界一般」「世の中」の考え方と柳田はこの点で通底することは既に述べた。不戦条約の理念が国民に根ざすべきだ、という考え方が踏みにじられる姿を目撃したのである。
だから初版の出版年1928年、そして再版の1931年という文脈はただ「不戦条約」だけでなく更にもう一つ、「人民ノ名ニ於テ」、つまり日本という国の主権者が「平和」を選択することを「天皇」を方便に奪われる過程であったのだ。「方便」と記すのは、この事件が政党間の「政争」としての側面が強くあるからである。「天皇」を政治的思惑の中で利用することは当時だけでなく「現在」でも繰り返されていることは言うまでもない。
このような経緯があったことを踏まえると、枢密院顧問官・柳田國男が不戦条約の理念の延長にある日本の憲法の草案審議に加わったことは、更に、深い意味を持つことがわかるだろう。「日本国民」によって「正当な選挙された国会」が、その名に於いて「不戦条約」の理念を継承する憲法前文を語ることは、枢密院がかつて、批准されなかった「人民ノ名ニ於テ」を改めて枢密院が復活させた意味を持つ。昭和天皇が天皇の名に於いて戦争を終えなくてはならなかったのに対し、戦後の平和主義は、天皇の大権から「人民」(つまり「国民」)に委譲されたのである。
柳田が立ち合った枢密院における憲法草案審議はその手続きの場であったともいえる。
このような歴史への責任感と自負が柳田の「憲法の芽を生やさねばならぬ」という遺言となったことがわかってくれるとうれしい。憤りも、改めて伝わって来るだろう。
このように、毎回、柳田の文章を少しずつ、丁寧に、時代背景を踏まえ、その上で現在との関わりの中で読んで行こう。その作業の中で、柳田國男が構想した彼の学問、つまり、主権者教育としての民俗学について、それがどのように構想され、どのように実践され、どのように頓挫したのかを理解しよう。そして、もう一度、彼の学問の可能性について、真剣に考えてみようと思う。
『青年と学問』より
公民教育の目的最近に諸君と会談してから、はやすでに三年あまりを過ぎた。あの後日本にはいろいろの事が起り、好(よ)い事もあったが好くない事の方が多かった。自分としてもこの三年の間に、少々弱ったと見えて生活がかなり重荷(おもに)である。それにもかかわらず、かつて我々が民族の前途のために、幽(かす)かなる一道の光明のごとく感じていたものが、この三年間にもしだいに成長して、世の中は大分(だいぶ)明るくなってきた。通例人の通例の努力をもってしても、以前に比べるといろいろの事物が、ややはっきりと見えるようになった。智識の真の楽しみが認められまた求められるようになった。学問のみが世を済(すく)うを得ベしということを、信ぜざるをえぬようになった。
(中略)
学問なんか何のためにするかという質問は、じつはもと我々には不愉快なる軽蔑(けいべつ)の言葉に聴(きこ)えた。俗物め、何を言うか、およそ人間の努力、人間の携(たずさ)わり得るほどの事業の中で、これが最も高い種類のものなのだ。実利世用の有無などは問うところでないのだと、独(ひと)りごとには言い切っておりながらも、実際は内心窃(ひそ)かに煩悶(はんもん)をした人が多かったのである。学問というものが、たんに塵(ちり)の浮世(うきよ)の厭(いと)わしいゆえに、しばしはこれを紛(まぎ)れ忘れようとするような、高踏派(こうとうは)の上品な娯楽(ごらく)であるか、はたまた趣味を同じうする有閑階級に向って、切売小売(きりうりこうり)をなすべき一種の商売であるならばいざ知らず、断じてその二つのいずれでもないことを信じながら、なおこれほど眼前に痛切なる同胞多数の生活苦の救解と、いまだなんらの交渉をも持ちえないというのは、じつは忍びがたき我々の不安であった。それがこの頃になってから、たとえ少しずつでもしだいにその応用の途(みち)に目を着けようとしてきたのである。
(中略)
世の中の実務の方でも、年一年と学問から遠ざかって行くかのごとき感がある。げんに政治の方面などを見ても、故事や前例を引くような人は、多くはその説が迂愚(うぐ)笑うべきものであった。今日の実際に適切でないために、人から軽く視られていた。ところがよく考えて見ると、これにはもとより方法上の欠点もあったが、第一には世人が歴史の智識の応用を誤まっていたことが、かくのごとき悲しむべき疎遠(そえん)を余儀なくしたのである。それからまたこういう学問に対する世間の態度も、正しいとは言われぬように思う。史学は古い事を穿鑿する技術ではけっしてない。人が自己をみいだすための学問であったのだ。だがそういう風には自他ともに考える人が少なかった。
現在のこの生活苦、もしくはこうして争いまた闘わねばならぬことになった成行(なりゆき)を知るには、我々の持つところの最も大なる約束、すなわちこの国土この集団と自分自分との関係を、十分に会得(えとく)する必要がある。それを説明する鍵(かぎ)というものは、史学以外には求めえられないのであった。我々がただ漠然と国の姿といい、あるいは時代の風などと呼んでいたものを、具体的に理解するためには、何よりもまず一個民族としての日本人を意識する必要があったのである。
今が今までぜんぜん政治生活の圏外(けんがい)に立って、祈禱祈願(きとうきがん)に由(よ)るのほか、よりよき支配を求めるの途を知らなかった人たちを、いよいよ選挙場へことごとく連れ出して、自由な投票をさせようという時代に入ると、はじめて国民の盲動ということが非常に怖(おそ)ろしいものになってくる。公民教育という語が今頃ようやく唱えられるのもおかしいが、説かなければわからぬ人だけに対しては、一日も早くこの国この時代、この生活の現在と近い未来とを学び知らしめる必要がある。しかもそれを正しく説明しうるという自信をもっている人がそう多くないらしいのである。ここにおいてか諸君の新らしい学問は、活(い)きておおいに働かねばならぬのである。異人種観の改良
歴史の学問も現在の研究程度に止まっているということは、無用なるのみかまた有害でもありうる。いわゆる軍事教育が日本人を「戦う国民」とするという懸念(けねん)は、おそらく絶対にないこととは思うが、すくなくとも民族間の真の平和を、積極的に求めようとするには、これだけでは足りないことも確かである。我々はなおこれ以上に、公(おおや)けに国際の正義を論じ得るだけの、力と自信とを養って置かねばならぬ。
申すまでもなく国防の第一線は、毒ガスでもなければ潜水艇(せんすいてい)でもない。まず国と国との紛争を解決すべきものは、討論であり主張であり、不当なる相手方の反省であり屈伏であるわけだが、現在各国の持っている国際道徳は、不幸にしてまだ我々の個人道徳と、同列にまでも進んではきていない。省察もなければ悔悟もなく、またしばしば曲解があり我執(がしゅう)がある。今往古来これがために無用の殺戮(さつりく)が行われ、亡(ほろ)びずともよい多くの国が滅(ほろ)んだ。しこうして敵を滅してこれによって栄えようとした国が、往々にして成功している。その結果戦争必要論は今もって有力なる政治家等の窃(ひそ)かにこれを信ずる者が多いのである。しかし世界一般から言うならば、もう沢山(たくさん)だと考え出したものがはるかに多数を占めている。遅々たる歩みには相違ないが、今や何かこれに代るべき手段を発見しようということに、世の中がなってきたのである。代るべき方法はそう多く有るべき理由がない。結局は自ら知り、たがいに今までよりも一段と精確に、争いの原因と結末とを考えて見ることのできるようにするより以上、べつに新奇なる発明があるべきはずはないのである。ところがいわゆる治乱興亡の跡を詳(つまびら)かにすという一つの学問が、いかなる理由があってか今日までは、まだ本当によく働いてはいなかったのである。どのくらい完全に今ある史学の智識を消化しても、それのみではまだ平和本位の国際主義を、成立せしめるには足(た)らなかった形がある。
過去の日本がこの島々の中において、しずかに仲よく一国限りの平和を楽しんでいた時代にも、外から来る者はみな敵と認め、日本国民でないものはみな一つに固まってあたかも舌切雀(したきりすずめ)の婆の葛籠(つづら)の中から飛出す者のように、いつかは寄ってたかって我々を犯すであろうと考えることは、無益にしてかつ結局は損失であったが、いよいよ同胞がこの小さい島々に居(お)りあまり、もうこれから外へ出て何か仕事を見つけるほかはないという段になると、ことにそのような大ざっぱな異人種観は邪魔(じゃま)ものである。異人の中にもいろいろあって、顔でも言語でも服装でもする事でも千差万別である。傲慢(ごうまん)で調子づいている者もおれば、遠慮ばかりしてなおいじめられているのもいる。それが同じ国の者でも時と境遇によって、また一様ではないのである。国と国との利害は錯綜(さくそう)しており、彼らどうしでもやはり争いまたは和している。その間の交渉が日を逐(お)うて面倒になり込みいってくる上に、此方(このほう)の立場も人によって統一がないわけで、こうなるともはや出先(でさき)の外交官や、時の武人団の意向などに、和戦の判断の鍵を委(ゆだ)ねて置くわけには行かぬ。国民自身が直接に、この重要なる根本問題を考えて見なければならぬ。すなわち普選はいわばそのための普選であったのである。