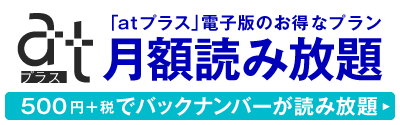『郷土生活の研究法』を読む/内省する社会
柳田國男は自分の学問を規定する時、好んで「反省」や「内省」ということばを使う。「自己内部の省察」という言い方もするが、意味は同じだ。自分らのあり方を省察するという意味での「反省」を万人のものとしたのは、言うなれば近代の功績である。後述するように、柳田は「省察は近代の傾向」という言い方でこのことを指摘してもいる。
事実、省察は明治30年代、一種の流行であった。明治36年(1903年)5月22日、華厳の滝で投身自殺をしたのは慶大生・藤村操だが、彼が傍らの木の皮を剥がし書き残した遺言「厳頭之感」が、内的な煩悶であることからその死をめぐる議論は社会現象化し、「省察」の流行ぶりを物語っている。それより前、明治29年、田山花袋と島崎藤村は自作の抒情詩の原稿を華厳の滝の前で朗吟し、原稿を滝壷に放り精神を捧げたという逸話も残る。彼らは松岡(柳田)國男とともに合同詩集『抒情詩』を刊行するが、近代の青年たちにとって華厳の滝は「内面」を捧げる象徴的な場所として選ばれていたのは、偶然かもしれないが、興味深い。近代における「内面の発見」は、ある意味、世俗的大衆的であったことは忘れるべきでない。
詩人としての松岡國男が田山花袋と一瞬、併走した近代文学は、最初、彼らの中では、「私」の内面を「感じたるまま」に歌う新体詩として出発した。花袋は「私」の内面を観察する近代小説をつくり、柳田國男となった松岡國男が向かったのは、「個人」でなく「社会」を「省察」の主体とすることと、その手段としての学問づくりだった。その「学問」こそが「文学」だとこの時期の柳田は考えていたとさえいえる。
今回は、この、柳田國男の「内省する社会」という考え方をその文章から読みとっていきたい。
そもそも、この国では現在、「社会」という責任主体が明らかに希薄になっている。あるいは人々がそのような意味での社会から撤退しようとしてはいないか。
例えば、一人の少年が犯罪を犯した時、それを「社会の問題」として受けとめようという声は掻き消されがちである。このような時「自己責任」や「親の責任」がまず語られる。弱者を社会の責任で引き受けるという立論を政治が放棄しかけているのは多くが感じるところだが、それが間違っているという人は、もはや必ずしも多数派ではなくなっている。
社会の問題、とはいうまでもなく、「私たちの問題」なのだが、それを認めたくないためなのか、何か事件が起きると、いわゆる「在日認定」、つまり事件の当事者は日本人ではないというトランプもどきのオルタナティヴ・ファクト(もう一つの現実)が必ずと言っていいほどツイートされるが、それはは社会の問題を「私たち」の外側に追いやるさもしいレトリックにもとれる。
自分の恋人でも友人でもないタレントやモデルが不倫をするとTVモニターから謝罪し許しを乞われなければいけない光景をうんざりする程目にする。彼らが許しを乞う相手は、不倫したタレントの配偶者でも恋人でも二股の一方でもない、「誰か」である。
その「誰か」とは誰なのか。
一方、「社会」の代わりに頻繁に用いられるようになったのが「日本」である。しかし「日本」が責任主体となり、アジア諸国に対して「反省」することは「自虐史観」として、今や、唾棄される。歴史への「内省」は「反日」的行為に他ならない。一方で「日本凄い」系の新書やテレビ企画が溢れ返り、あるいは、テレビのコメンテーターから普通の人々のツイートまであらゆるタイミングで「日本を誇る」ことに熱心のように思える。
「社会」とワイドショーの不倫ニュースの視聴者と「日本」を一緒にするな、という反論もあろう。しかし、これらのことから現在のこの国の「社会」の姿が確実に見えてくる。
今、この国で「社会」は、
①内省をせず自らを誇る
②責任を引き受けないが謝罪を要求する
という属性を持っているように感じる。
そしてこう書くと、ある人は、それは日本でなく、アジアの隣国のことだと怒るだろう。また別の人は、まるでトランプ以降のアメリカそのものだと他人事のように語るだろう。
いくつかのトランプ以降のニュースから伝わってくるのは、トランプ支持者はグローバリズムから忘れ去られたアメリカの白人労働者だけではない、ということだ。アメリカの学校でも「アメリカ人でごめんなさい」と教育されてきた(アメリカのリベラリズム的教育のことだと思う)若者たちがトランプの物の言い方に「アメリカの誇り」をとり戻している、という指摘もある。(BLOGOS - アメリカ人でごめんなさい~トランプ就任式で聞いたふつうの人の声)それは、「自虐史観」批難と「日本凄い」が対になったこの国が、先どりしてきた事態だが、そのような「内省」は語られにくい。
「社会」のありかたをめぐって、一つの共通のこととして言えるのは、日本でもアメリカでも韓国でも多分、イギリスでもフランスやその他の国や地域でも「社会」という責任主体としての「私たち」が見えにくくなり、代替物の「われわれ」、つまり、流行の言い方に即して言えば「代替的社会」が輪廓を結び、それがナショナリズムや愛国を擬態していることではないか。この「代替的社会」の属性は、自ら責任をとらず、他人の責任は追及し、ただ自らを誇る、というものだ。付け加えれば、常に被害者として自己規定し攻撃的だ。
そして何よりも特長的なのは、自分たちの姿は、このようかもしれないと「内省」することができない、ということだ。その証拠に、私たちはトランプやその支持者を見て、私たちのようだと「内省」できない。
そもそも「社会」というものを「内省」の主体として発見したのは、柳田も言うように「近代」である。資本主義システムが西欧で駆動しはじめると、王の善政(というのは本当はあったためしがない)や宗教的な祈りや個人の努力では解決できない、社会システムそのものが必然的に生み出す「問題」が生じる。資本主義は「優勝劣敗」(北村透谷)、つまり勝者が敗者を淘汰するという自由競争が基本ルールである。これはダーウィンの進化論が「近代」にエンジン、あるいはOSとして埋め込まれたからであり、進化論ルールの適応を人間の社会や経済にまで敷延したものである。それが自由主義である。こういった社会ダーウィニズムの論者の一人が忘れ去られた(というより耐用年数の尽きた)思想家であるハーバート・スペンサーだが、俗流ビジネス書のような主張が存外の影響力を持ち、その著作が明治30年頃までは東京帝国大学の教科書に多数、使われていた事実がある。
このような社会ダーウィニズムは必然的に「敗者」を産む。敗者が多くの「負なるもの」を背負わされる。それを自己責任とせず、「社会問題」と名付け、「社会」によって解決していく手段として生まれたのが、社会政策論という考え方だ。その中で急進的な考え方をしたのが社会主義者になる。
このような大雑把な文脈を踏まえれば、明治35年、文学、つまりロマン主義を捨て社会に着地しようとしていた柳田國男の以下の発言の意味が改めて見えてくる。
日本の中で社会主義の人であるとか、又は社会問題を研究するといふ人でも、見渡す処真面目にヤツて居る人が実に鮮い様に見えます、(中略)社会問題の研究は元より結構な事である計りでなく、私も実際此側のものなのです
(「柳田法制局参事官の談片」『河北新報』明治35年8月22日、河北新報社)
この談話から、柳田はこの国の近代で「社会問題」を発見し、「社会政策」の側に意図して立とうとした一人であることがうかがえる。
この時期の柳田は農業政策に関わる農政官僚である。地主と小作の関係が近代の資本主義経済に組み込まれ生じた「貧しさ」を、国策に従わせ、助成金でそのごく一部を購うという現在に至るこの国の農政とは異なり、資本主義システムの中で農業に実際に従事する人々の経済的基盤をいかにつくるか、という社会政策の「側」に柳田はあった。明治30年代、足尾鉱毒事件がまさに「社会問題」として浮上するが、当時、その「研究」に関わろうとした事実も、どこまでコミット出来ていたかはともかく、柳田が「社会問題」を通じて「社会」を発見した明治青年だった傍証にはなる。
大塚英志寄稿:次のページ