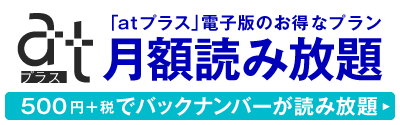さて、『民間伝承論』『郷土生活の研究法』の中で、柳田は「心意」ということを問題にする。柳田の学問が「心意」をこの時期から中核に据えたことは柳田論でつねに議論のまとになっていたが、やはり、「内省」の問題として考えるべき問題だといえる。
「心意」という問題は民俗資料の三部分類として『民間伝承論』の中で以下の用に定義されることがよく知られる。
すなわちまず目に映ずる資料を第一部とし、耳に聞える言語資料を第二部に置き、最も微妙な心意感覚に訴えて始めて理解できるものを第三部に入れるのである。目は採訪の最初から働き、遠くからも活動し得る。村落・住家・衣服、その他我々の研究資料で目によって採集せられるものははなはだ多い。目の次に働くのは耳であるが、これを働かせるには近よって行く必要がある。心意の問題はこの両者に比してなお面倒である。自分は第一部を洒落(しゃれ)て旅人学と呼んでもよいといっている。通りすがりの旅人でも採集できる部門だからである。これに倣(なろ)うて第二部を寄寓者(きぐうしゃ)の学、第三部を同郷人の学ともいう。
(柳田國男「民間伝承論」『柳田國男全集28』1990年、筑摩書房)
この時、第三部としての「心意感覚」を「同郷人の学」という言い方を柳田はする。それは読み方によっては「郷土」以外の人々には「心意」は研究できない、そこから敷延して「日本」のことを「日本人」しかわからない、という誤解を招きかねないものだ。
しかし、柳田は「心意」を「郷土人」の領域とするのは、既に見たように「郷土」を「内省」の主体としてこの書では置いているからで、内省はまさに当事者にしかできず、第三者はできないのである。
つまり柳田の言う「心意」研究とは、「自己内部の省察」なのである。そのことは以下のように明確に示される。
我々の学問は結局世のため人のためでなくてはならない。すなわち人間生活の未来を幸福に導くための現在の知識であり、現代の不思議を疑ってみて、それを解決させるために過去の知識を必要とするのである。すなわち人生の鏡に照してわが世の過去を明らかにせんとする、歴史の究極の目的は眼前にぶら下がっているのである。そのための採集は、いわばそれらの不可解な事実を精確に記録し表現することであるが、それが表面の事実ならとにかく、郷土人の心の奥の機微は、外から見たり聞いたりしたのではとうてい分りようもなく、結局彼等自身の自意識に俟(ま)つよりほかに仕方はないのである。つまりは我々の採集は兼ねてまた、郷土人自身の自己内部の省察でもあったのである。
(柳田國男「郷土生活の研究法」『柳田國男全集28』1990年、筑摩書房)
このような、「自身の自己内部の省察」として出発したから、戦後の彼の学問もまた「内省」の学として出発することになる。この国の戦後は、戦争に負けて付け焼き刃で、あるいは戦勝国やアジアからの圧力で「内省」したのではない。このような「内省の学」が戦時下に準備されていたのである。
ところでもう一点、ここで注意したいのは、このような「内省」という手続きは、「無意識」の可視化に他ならないということである。以下に『郷土生活の研究法』の「結び」である。
これを要するに、現代の生活事実の中を、新時代にかぶれている部分がどれだけ、現代のインテレクテュアルな部分がどれだけ、それからまた無意識にやっていることがどこまで、とはっきり分けてみることがこの学問の一つの目標である。こう言ったらあるいは、そんなことをしていたら他のことは一つもできやしないではないか、という人があるかも知らぬが、だいたいに省察は近代の傾向であった。学問の世間的用途を力説するのは、あるいは卑窟に聞えるかも知らぬが、知識であり同時にまた技術でなくてはならないと思うのである。結局事実を知るということは、それが単に知っただけの知識で終るのでなくて、さらに批判し推理する知識とならなければ、学問は無意味になってしまうのである。
(柳田國男「郷土生活の研究法」『柳田國男全集28』1990年、筑摩書房)
柳田は「われわれ」の行為のどこまでが「無意識」に規定されているかを腑分けすべきだと言う。この時期、民俗学の方法化を試みる時期の柳田が「無意識」ということばを頻繁に使うことに、以前、注意を促したことがあるが、これはフロイドの使う「無意識」を指している。それを「省察」するのがそもそも「近代」の作法だと柳田は言うのである。
ここで重要なのは、柳田にとって「社会」の「無意識」は可視化し、克服すべき対象だということである。「民俗」という「無意識」に知らず知らずのうちに規定されている私たちは、「近代」というものを正しく迎え得ない。柳田をロマン主義と錯誤すると、ここを読み誤る。
柄谷行人は「憲法」が戦後日本人の「無意識」としてある、と主張する。しかし、柳田にとって「無意識」は克服の対象であり、公共性は「内省」によって意識の領域で達成されるものだと考えている。つまり「社会」は「意識」である。
前回見たように柳田は戦後憲法をこの国に根付かそうと試みた。それは、憲法の「意識化」に他ならない。
「憲法」にいたる「内省」の手段として柳田は戦後の彼の学問を定義した、といえる。その意味で社会は「憲法」の主体となる。
だから、『郷土生活の研究法』に於いて「社会」は「内省」する主体であるとともに、「学ぶ」主体でもあることに注意しよう。
同書はこう結ばれるのである。
郷土研究の方面にことに新たなる疑問のいまだ答えられざるものが多いということは、私たちから見れば大いなる希望である。社会はまだいくらでも賢こくなることができる。どうか諸君もその心持をもって、この学問の成長を観ていてもらいたいと思う。
(柳田國男「郷土生活の研究法」『柳田國男全集28』1990年、筑摩書房)
私たちは「社会を賢くすること」を断念すべきでない。