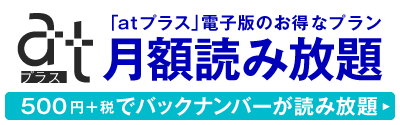「世間話の研究」における議論の筋道を確認しよう。
まず、柳田は、「ハナシ」と「語り」を区別する。
この一種の古風な物の言ひ様、即ち形に囚はれた一方だけの長広舌を、日本語ではカタリ又は物語と謂つて、無論世間話などのハナシとは別物としてあつた。カタルといふ動詞は既に零落して居る。
(「世間話の研究」『綜合ヂャーナリズム講座 第11巻』雑誌ヂャーナリズム、記事篇、昭和6年10月20日、内外社)
「カタリ」とは形式性に支配されたことばで、ことばのリズムや拡張によって人を引きつけるものだ。
それは、「語り物」「講談」といった口承の物語に向いた形式である。そこでは「内容」の真偽の検証は不問でその「形式」や「格同調」に説得力の根拠がある。
我々は所謂神話時代のやうに、もはやあの内容を事実として承認せぬのだが、上手にあの形式で語られると泣きたくなる。形式そのものゝ力か、はた複雑なる歴史的聯想の為かは知らず、まさしく彼には魅力があり、従つて存在理由がある。
(「世間話の研究」『綜合ヂャーナリズム講座 第11巻』雑誌ヂャーナリズム、記事篇、昭和6年10月20日、内外社)
いわゆるフェイクニュースがロラン・バルトの言う雑報(つまり一編のニュース記事単独で物語構造として閉じていること)としての形式性を持ち、独白の語り口で語られることを連想させる。柳田はだから、「カタリ」や「ハナシ」は「区画を明らかにして併存」すべきである、と言い切る。
但し少なくともこの二つのものは、区劃を明かにして併存し得るものだと、自分たちは信じて居る。
(「世間話の研究」『綜合ヂャーナリズム講座 第11巻』雑誌ヂャーナリズム、記事篇、昭和6年10月20日、内外社)
つまり、物語の形式と文体は物語に帰結せしめよ、ということだ。それは言うまでもなく、「物語構造」を知ることで現実を語ることば(ニュース)に侵入した「物語の構造」を見抜くリテラシーとする、ぼくの物語ワークショップで目的のひとつと当然、時を隔てて連なるものだ。
その上で柳田は「物語るための文体や形式」が、社会を「ハナス」ことばに混入していることを問題視するのだ。
独り世間話のみが依然として人間の需要を開拓せず、楽な昔風の御伽坊主の職業意識を、踏襲させようとして居たのは無意味であつた。又歎息すべき損害でもあつた。
(「世間話の研究」『綜合ヂャーナリズム講座 第11巻』雑誌ヂャーナリズム、記事篇、昭和6年10月20日、内外社)
「御伽坊主の職業意識」とは、昔話を「カタル」文体で社会を「カタル」あり方を言う。そこから社会を「ハナス」ための「話」を分離しなくてはいけない、というのが柳田の主張である。それは「ゴシップ」「流言」「内緒話」といった「ハナシ」もまた「カタリ」の形式に支配されているからに他ならない。つまり
全体にパブリシティーを既に定まつた形式と、結び付けたまゝで置くのが悪かつた。
(「世間話の研究」『綜合ヂャーナリズム講座 第11巻』雑誌ヂャーナリズム、記事篇、昭和6年10月20日、内外社)
のである。
ここでいうパブリシティーとはマーケティング的な「宣伝」ではなくて、公共的なことばの意味である。
だからこそ柳田は「世間話」をこう定義し直す。
併し少なくとも世間話といふ名は当つて居る。セケンは実際の日本語に於ては、今の社会といふ新語よりも意味が狭い。是に対立するのは土地又は郷土で、つまり自分たちの共に住む以外の地、弘く他郷を総括して世間とは言つて居たのである。
(「世間話の研究」『綜合ヂャーナリズム講座 第11巻』雑誌ヂャーナリズム、記事篇、昭和6年10月20日、内外社)
この「世間話」という語の「よみかえ」こそが重要である。
流言や内緒話は「閉じた」ことばである。流言や内緒話を「カタル」ことで「われわれ」が再確認されていく様は、たった今、webでいくらでも確認ができる。
しかし柳田は「世間」を「われわれ」の「外部」とする。単一の「郷土」の「外」を柳田は「世間」だという。
「郷土」という「内」に対して、「外」を可能にすることばを柳田は「世間話」からイメージするのだ。つまり、「世間話」とは閉じた世界同士を繋ぐことばなのである。
だから柳田はこうも言う。
地方版が発達して、我々の世間話が、外国と中央と各自の県内とに限られ、嶺一つ彼方へ越えれば何事が起つて居るのやら、知らずに日本人が互ひに結合して居るのを、歎かはしいことのやうに考へて見た人もあつたが、その世間話が本当のものにならぬ限り、仮令境を撤廃して筒抜けにして見た所で、格別我々の生活実験が、今よりも地平線を弘くしてくれることは無さゝうである。
(「世間話の研究」『綜合ヂャーナリズム講座 第11巻』雑誌ヂャーナリズム、記事篇、昭和6年10月20日、内外社)
柳田は新聞の地方版と全国版の不連続に言及する。地方版が地方のものしか扱わず、他方はいきなり「日本」を扱う「中央」のニュースに切断される。そうではなくて、「閉じた世界」(郷土)を「結合」していく「ことば」として柳田は「世間話」を定義したといえる。つまり「世間」とはパブリックであり、だとすると「世間話」は「公共的なことば」なのである。
先に引用した「ハナシ」が「同種族を繋ぎ合わせる」手段となる、というのは、人々がこれから「公共的なことば」で繋がっていく、ということである。
しかし、こう書いた瞬間、そのことばは今の時代では「絆」とか「日本」といったキーワードにとって替わるだろう。このようなキーワードが「公共的なことば」であり、あるいはただ、「教育勅語」を暗唱することでそれに替える、という議論に流される。繰り返すがそれは「世間話」ではない。
柳田はこと話にキーワードで結びつけと言ってはいない。
他人と同じことばを暗唱し繰り返すことでもない。
そのことは、昭和18年、つまり戦時下に
永い間に覚え込んだ沢山の言葉を、自在に組合わせてこそ自分思つたことが言へる。文句丸呑みだつたら鸚鵡ぢゃ無いか。自分の生活とは言へないでは無いか
(「教育と国語国策」『教育』岩波書店、昭和18年4月~6月)
と、言いはなつ態度にまで一貫している。
「公共的なことば」とは「社会」をつくっていく「ことば」である。「語る」とは、借り物の形式である。内緒話、流言、噂は他人のことばのコピペであり、他人に非言語的に同調するツールである。対して「ハナシ」は、自分のことばである。「世間話の研究」では、有権者は自分のことばを話し、として他者と繋がることで社会は可能になる、そして、「内緒話」でなく、人と人、地域と地域を繋ぐ「公共的なことば」が語られる場に新聞やジャーナリズムはあるべきだ、といっている。
幾度でもいうが、web以降のメディアのあるべき姿が、かつて、紙のメディアをめぐってかくも論じられていたのである。
柳田國男「世間話の研究」より抜粋
我々の国語利用法が、それではなる程発達しなかつた筈だと、早合点せられても少し困るのは、順序が其様に簡単なもので無つたからである。ハナシこそ通常人の常の日には用の無いものであつたが、一生を通じて見ると言語の働きは、却つて昔の方が念入りであつた。お経といふ莫大な文字が、其内容の理解とは無関係に毎日あの通り熱心に読まれて居たのを見てもわかる様に、或は又たつた一つの簡単な唱へごとが、何百万遍でもくり返されて居たと同じく、いざ入用となれば言葉を惜まなかつたことは、余裕が多いだけに昔の人の方が遥かに基だしかつた。啞でも吃りでも決して無かつたのである。 人が鳥獣で無い本当の有難味、言語のねうちといふものを心の底から感じて居た為に、之を粗末には取扱はなかつたゞけである。主要なる用途は弘い意味の社会教育、即ち後から生れて出た者に、是だけは必ず伝へて置かなければならぬと、信じた問題ならば十二分の言語数を費して居た。さうして其問題と場合とが、最初のうちは特に限られて居たやうである。人がたゞ漠然と神話時代と名けて居るものが、又此中に含まれることは勿論であるが、さういふ気風はずつと後までも続いて居た。改まつた折の言語の感動を深く強くする為に、常は成るべく無口で居らうとする心掛けも普通であり、一方には又さういふ晴の日の語りごとを、大事にしたことも一通りでは無かつたので、我々の所謂文法も修辞法も、実は殆ど其全部が、この方面から発達して来て居ると言つてよかつた。但し神話とはよく言ふけれども、それは我々のハナシでは無かつた。近頃斯んな名称を考へ出した人たちが、まだ「話」と其以前の言語利用法との差別を、はつきりと知らなかつたといふだけである。村の住民は却つて意識に忠実に、今でもこの二つのものゝ相異を解して居る。たとへば村会の席上だけでは、近隣のゴテ等を諸君と言つたり、デガンスを「であります」と言つたりして居る。即ち大昔以来の慣行に遵うて、晴の日に限つて切口上を用ゐ、言葉を改めなければならなかつたのである。文学が現代日語に由るといひつゝも、尚しばしば前人の型を追うて居るのも、さては盆正月や吉凶の式に際して、耳を聳てるような挨拶の文句を聴くのも、言はゞ日常の会話などゝ混同せられまいとした努力の名残であつた。其中でも伝承を主眼とした往古の実蹟、神の奇瑞とか家々の由緒を説くやうな場合には、印象を強烈に、記憶を容易ならしめる必要から、特に荘重なる言葉を択んで句形を揃へ、又屢々譬喩のやゝ意外なるものを用ゐた。韻や対句の起原は別に有つて、 必ずしも同じ目的の為に発明せられたものでは無いらしいが、是も此場合には盛んに利用せられて居た。それに第一は余りにも一くさりが長かつた。よほど熱心で他念も無く聴き入る者を、相手にして居ないと飽きられるのは自然であつた。之に比べるとハナシが簡略で、且つ気の利いたものゝやうに感じられることになつたのも、時節の致すところ奈何ともせんすべは無かつたのである。
この一種の古風な物の言ひ様、即ち形に囚はれた一方だけの長広舌を、日本語ではカタリ又は物語と謂つて、無論世間話などのハナシとは別物としてあつた。カタルといふ動詞は既に零落して居る。騙して人の財を捲き上げることをさう謂ふのは、如何なる過程に導かれたものか知らぬが、今一つは小児が遊戯に参加することをカタル、又は男女相許すこともカタルと謂つて居る土地がある。起りは皆一つで独り言の反対、即ち聴き手が多人数であることを条件として居たものと思はれる。物語の興奮も是れを大いなる刺戟として居た如く、衆と共に耳を傾けるといふ面白さだけが、いつ迄もこの昔の形式を引留めて、やゝ又新たに生れた色々の話の中にも、若干の影響と拘束とを付与することになつたのである。生活価値の問題が省察せられる世の中になると、斯ういふ外観ばかりの伝統は実際は無意味であり、時としては又煩累ですらもあるのだが、我々日本人は永い年月の親しみに由つて、今尚この空虚なる格調に深い愛着を持つて居る。たとへば唯物史観に徹底したやうに言つて居る共産党員が、うつかり法廷で「某の霊を慰める為に」と激語して、挙げ足を取られたなども其一つの表はれであり、折角自由に発展しかゝつて居る今日の世間話が種の方からも又話術の方からも、直ぐに類型に堕ちて下らぬものになつてしまうのも、有りやうはこの美しい言霊の国に生れながら、古今の言語芸術の是ほど顕著なる分堺に心付かず、いつ迄も株を守つて兎を待つやうな、酔狂なる態度を棄て切らぬ為であつた。そういふ拙者なども恐らくはその迷ひ子の一人であらうと思つて居る。
但し少なくともこの二つのものは、区劃を明かにして併存し得るものだと、自分たちは信じて居る。一方を突倒して根こそぎにしなければ、次のものが栄えぬといふ風には思つて居ない。カタリの今日も尚活きて居るのは、謡は兎に角として浄瑠璃などは確かにそれである。是も以前の扇拍子を物足らずとして、便利な小楽器などをあひの手に入れた為に、歌だ音楽だと思つて居る者が有るか知らぬが、実際はたゞ事柄を人に伝へる古臭い一つの方法なのであつた。我々は所謂神話時代のやうに、もはやあの内容を事実として承認せぬのだが、上手にあの形式で語られると泣きたくなる。形式そのものゝ力か、はた複雑なる歴史的聯想の為かは知らず、まさしく彼には魅力があり、従つて存在理由がある。今後も残して置いて相応な役目を勤めさせるはよい事だと思ふ。たゞ問題になるのは我々の常の日の交通、有りのまゝを説かねばならぬ演説や手紙や新聞に、何とかしてさういふものを加味したのが上手と、御互ひに感じて居ることがいゝか否かである。中河与一氏は僕の近所に住んで居るが、同君の形式は白由な創製品で、決して神代前から制定せられてあつたものを、発掘して来て用ゐようといふのでは無いらしい。併しそれでも此形が最も適すときまることは、同時にそれを是認する者が親しみを感じて、やゝ不必要に永くつらまつて居ることに帰着する。時と境遇と各自の情感とに、毎回調和したものを選定してよいのならば、寧ろ形式といふ字を使はぬ方が便だと私は思つて居る。それは此序に論じ尽す能はずとしても、兎も角も我々の世間話は囚はれて居る。以前カタリが博して居た喝采をそのまゝ相続しようとするので形式が古くさい。さうして其為に世の中が馬鹿に淋しい。