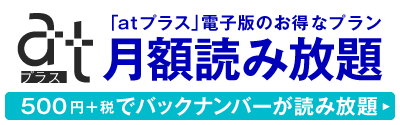「祭礼と世間」を読む/柳田國男の「群衆」論
ボイド(Boids)と呼ばれるCG用のプログラムがある。1986年にCGの専門家レイグ・レイノルズが開発した鳥の群れの動きを再現するプログラムである。数百、あるいは数千かそれ以上の個体からなる鳥の群れが無限に変化する動きをシミュレートするプログラムは、さぞかし複雑だと素人は考えるが、そのためにプログラム上の「鳥」に命じたのは以下の3つの規範だといわれる。(ピーター・ミラー著『群れのルール 群衆の叡智を賢く活用する方法』東洋経済新報社)
1、他のボイドに近づき過ぎないこと。
2、近隣のボイドの向かう平均的な方向を自分の方向とすること。
3、近隣のボイドの平均的ポジションに移動すること。
この3つの命令だけで鳥の群れはCGで再現できる。
web上で検索すればレイノルズが作成したシミュレーション映像が簡単に見つかるはずだ。(参考 robottage: 模倣で生まれる群れの集合知 http://robottage.blogspot.jp/2015/06/boid.html)
紙飛行機のようなオブジェの群れが壁や円錐を回避して一つの意志があるように動いていくアニメーションが、このたった3つの規則で動いていると思うと、あらためて人間の群れ、すなわち、社会や群衆を成り立たせる規範もまた「ボイド」のようなものなのかと思えて来る。
そして、少なくとも「群れ」を制御するこの3つの規範は、集団における人間の思考回路とひどく似通っていることに気付く。
他人とは適切な距離をとり、「みんな」の進む方法に合わせ、より「みんな」が集まる方へと向かっていく。
リアルに於いてもwebに於いても人は案外このように動き、そして何より、ことばを紡いではいないか。
他人とのことばとことば、自我と自我の軋轢を回避するように適切な距離をとり、周囲の話題や論調に合わせ、多数派へと常に向かっていく。そんなふうに日々の会話、web上のことば、そして文学やジャーナリズムも「鳥の言論」としてある。そして、これらのボイドの規範に抵触をすると、言うまでもなくリアルに於いては空気を読まないと避難され、web上では炎上ということになるのではないか。しかも「鳥の言論」においては、参照する世界はひどく狭い。例えば鳥の群れというとムクドリをすぐに思い出すが、ムクドリの個体が参照するのは周囲の数羽で、それ以上だと情報が多すぎるのだという。リアルでも文学でもその関心が極めてミニマムな領域に向かうのも「鳥の言論」「鳥の文学」では、必然なのだろう。
このように、殆ど、ボイドの規範で現在の言論は説明出来てしまう気さえする。
『感情化する社会』を書く時、太田出版の人から山ほどの近頃のベストセラーを資料に送りつけられ四苦八苦して読んだのだが、又吉直樹だけでなく、むしろ批評に「鳥の言論」化が強いのが興味深かった覚えがある。ボイドを直接のモデルとしているわけではないが、集合知への一時期の礼賛などの背景には、言論を「鳥の言論」化する文学観・言論観の形成という問題がある。そのあたりが、本当はもう少し丹念に批評の対象にならなくてはいけない。
だが、こういった事態はwebがもたらしたものではなく、webが可能にしたのは、この「鳥の言論」の可視化と、参画のし易さである。むしろ近代を通じて「鳥の言論」は問題とされ、ポピュリズムやファシズムと呼ばれるものは、「鳥の言論」に「民主主義」が結びついた結果ではないか。
そう考えると、柳田國男が第一回普通選挙後の選挙民、つまり有権者をこう憤っていたのは改めて興味深いのだ。
あの選挙区なら何の某を抱き込むとおおよそ何百票だけは得られるということは、顔で投票を集められるような親分が、そこにいることを意味していた。(中略)個々の投票の売買ばかりを戒めても、まだまだ選挙が自由に行われているものと、推断することのできない理由は、こういう大小の幾つとなき選挙群が、単に一個の中心人物の気まぐれに従って右にも左にも動かし得たからであった。
(柳田國男『明治大正史 第四巻 世相篇』1931年、朝日新聞社)
柳田は、有権者が「個人」でなく、選挙民の群れであったことを問題視し、「選挙群」を「選挙民」たらしめる公民の民俗学を立ち上げるわけだが、このような問題意識の背景には「群れ」としての「人間」という新しい問題がある。今回はそのことについて整理する。
柳田國男はある次期から獣についての小文を熱心に書くようになる。しかし、それは柄谷行人が考えるような山人の代償ではない。例えば『孤猿随筆(こえんずいひつ)』(1939年)に収録された、動物の中に社会や習慣を見る生態学的議論の多くは、昭和初頭の普通選挙実施以降に集中的に書かれている。それらが実は群衆批判とでもいうべき文脈にあることを忘れてはいけない。東浩紀風にいえば、柳田はそこで、脱「動物」化の立論をするのである。
柳田の中で、こういった、脱「動物」化的な議論は、戦後も再度、浮上する。例えば『婚姻の話』(1948年)は、柳田が敗戦から間もない頃、彼の「公民の民俗学」をやり直そうとする時期に書かれた家族論だが、その冒頭一章も鳥たちの群れの観察に費やされる。
そして、その章における議論は以下の一節に収斂するのだ。
自然に生き榮える者の實例を見くらべただけでも、是が古來の現象で無かつたことは明らかであらう。今度はもう一度、個々の人から世を始めようといふに臨んで、是をもし考へて見なかつたら、或は鳥蟲よりも前に戻つてしまふことになるかも知れない。
(柳田國男「婚姻の話」『定本 柳田國男集第十五巻』1969年、筑摩書房)
つまり、人間がもう一度個人となるには動物から離脱すべきである、と柳田は明らかな「動物化」批判をしているのである。そのために「獣」について観察的に柳田は論じるのである。
大塚英志寄稿:次のページ