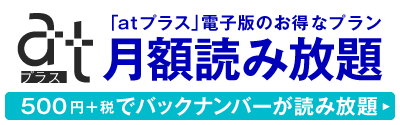こういった人間や民俗文化を自然科学的にとらえ直す柳田の論のたてかたは、柳田の中でロマン主義的民俗学が肥大した時に冷静さをとり戻す手続きとして必ず導入されるものだ。
柳田の学問が「ロマン主義」と「公民の民俗学」に双極的構造を持っていることはしばしば指摘してきた。それは、柳田國男の基本的な読み方である。今、柳田はロマン主義と公民の民俗学のいずれかに傾斜しているかを判断することで柳田の書は正確に読める。
そして、ロマン主義からの揺り戻しの際に、しばしば導入されるのが理系的な視点である。「獣」への視座はその一つである。この時、柳田は自身のロマン主義を自然科学的思考で常に超克しようとする。例えば『婚姻の話』を書く直前の柳田は、彼のロマン主義の源泉である孤児妄想が固有信仰論にまで肥大した『先祖の話』(1946年)を刊行している。『婚姻の話』はその反動として書かれているといってよい。
柳田國男のこのような社会への理系的視点は、遡ればゾラの実験小説論にまで行き着くが、集団としての人間を「群れ」として一度、理系的に見るという視点が明確になるのは大正11年(1922年)間の『祭礼と世間』である。
同書は、原敬に始まるといえる政党内閣の誕生(1918年)と短期での終結から第二次護憲運動(1924年)に至る時期に書かれていて、「小序」には「大正十一年五月六日再度渡欧の前夜」とある。つまりジュネーブの国際連盟への再渡欧の直前にまとめられた書であることがわかる。
しかし、この時点では柳田の中心的関心はまだ、「普通選挙」にはない。柳田は未だ大正デモクラシーに合流していないからである。
この論の直接的な執筆動機なったのは大正8年(1919年)3月10日、宮城県塩竃神社の帆手祭で起きた「神輿荒れ騒動」である。この祭礼では、十六人の氏子に担がれる神輿が町中の民家になだれ込み破壊するのが毎年の恒例であったというが、この年は民家4軒を破壊し、最後は塩竈警察署にまで突入し騒ぎが大きくなった。氏子と警察官との乱闘となり、氏子側が警察を不敬と避難、警察側は神輿の民家破壊が「神輿の影に隠れ私怨を晴さん」もので公安上、許しがたいとし、氏子と警察の対立に発展したようである。警察の見解では、神輿での破壊は対象となった家への氏子による私的制裁である、つまり、暴動なのだという主張である。
その騒動の渦中、現地に乗り込み調査を行ったのが東北理科大学の物理学教授・日下部四郎太であった。
そのことは以下のくだりに記されている。
東京朝日新聞の仙台通信によれば、東北大学の日下部博士は、これを信仰物理学と名づけておられるらしい。国幣中社塩竃神社の帆手祭に、神輿が暴れ廻って毎年三戸四戸の人家を壊し、本年などはとうとう警察署の構内まで乱入したので、官憲でも捨ておかれぬことになり、端もなくここに八百年前の山法師問題と、よく似た問題を再現することになったのを、右教授は頼まれて現場に出張し、何人でも「そうですか」と言わずにおられぬような報告をせられた。
(柳田國男「祭礼と世間」『東京朝日新聞』(1919年5月)、『柳田國男全集13』(1990年、筑摩書房))
この日下部教授の調査がどの程度世間の関心を集めたかはわからないが、柳田はその報告を待望していた、そして、この『祭礼と世間』という書を柳田側からの「歓迎辞」として書いたとさえ序文で以下のように記しているのだ。
ことに日下部博士の塩竃論が出ると聞いた時などは、我我は待つ船が着いた朝のような気持がした。この論文は実にその気持をもって、筆を執ったところの、一種の歓迎辞である。そうしてFolk-Loreの学問も、お蔭をもってその頃から、めきめきとして都鄙の間に盛んになり、ついにこの叢書なども要求せられるようになった。
(前掲書)
「この叢書」とは『祭礼と世間』が収録された「爐邊叢書」のことで、柳田の編集した雑誌である『郷土研究』休刊を受けてのものであった。
『郷土研究』は、柳田が自分の学問を「ルーラルエコノミー」と定義した時期の雑誌である。柳田はこの雑誌をヨーロッパ型の民俗学の雑誌にすべきだとする南方熊楠に「小生専門はルーラル・エコノミーにして、民俗学は余分の通楽」とまで言い切っていて、何なら雑誌は二つに分けたっていい、とまで私信で挑発的に述べている。ヨーロッパ型の民俗学はロマン主義文学の延長にあるから、この時期の柳田は嫌ったのである。
そして、彼の学問をこう定義していた。
先づ読者に説明せねばならぬ一事は、「地方経済学」と云ふ語のことです。記者の状にはさうは書かなかつた筈で、慥かにルーラルエコノミーと申して遣りました。(中略)政治の善悪を批判するのは別に多くの著述があります。地方の事功を録するものは「斯民」其他府県の報告が有り過ぎます。只「平民は如何に生活するか」又は「如何に生活し来つたか」を記述して世論の前提を確実にするものが此までは無かつた。それを「郷土研究」が遣るのです。
(「記者申す」『郷土研究』第二巻第七号、大正3年9月1日、郷土研究者)
「世論」形成の前提となる材料を集めるのが目的の雑誌であり、この雑誌に最後まで関わった物を中心に創刊したのが「爐邊叢書」である。だとすれば、そこに収録される柳田の著である『祭礼と世間』は、当然、「世論」がテーマになってしかるべきだ。
『祭礼と世間』に戻ろう。
「信仰物理学」と当時、日下部が呼んだらしい新領域は、この時期、柳田が模索中であった彼の学問、つまりロマン主義民俗学ではない「Folk-Lore」と共通点があると考えていることが、まずは先の引用からわかる。
しかし、信仰を物理学的に検証する、と聞くと明治期の井上円了による妖怪学、つまり「迷信」への科学的啓蒙を思い起こす。だが、決定的に違うのは神輿による家屋の破壊という集団的行動に物理学的関心が寄せられている点である。超常現象の科学的解析、つまりは、「信仰」の科学主義的否定でなく、神輿とこれを担ぐ氏子の「神輿荒れ」という物理運動の物理学的解析が信仰物理学のようだ。
そもそも、警察側がこの神輿を問題としたのは、既に触れたように、警察への乱入以前に、神輿を担ぐ者たちが毎年意図を以て任意の家を破壊しているのではないかという嫌疑にあった。つまり、これはある種の私的制裁ではないか、という疑念である。しかし、氏子は神輿の動きそのものは「神意」だと主張した。
日下部博士の信仰物理学からの解析は
教授の意見では、多数の人が神輿のごとき重い物を舁いであるくと、偶然に行列の路筋でないところにも、飛び込むものであるという
(前掲書)
ものであった。16人の担ぎ手の力が神輿の重心以外にランダムに加わることで、個々人の意思に反した動きとなり、制御不可能となった。だから、このような、物理的法則の中に「多数の人」、個々人の意志は反映され難い。それが日下部教授の結論であったことは柳田の言及からも窺える。その個人に制御することの出来ない動きが「神意」と解釈されたとも、日下部は当時の新聞(「東京朝日新聞」1919年3月18日)でコメントしている。
では、柳田は、この「神輿荒れ」という事件に「世論」をめぐるどのような問題をみたのか。
結論からいえば、「神輿荒れ」は旧式の世論形成システムであった、ということである。
そもそも、このような問題は塩竃に限ったことではない、と柳田は言う。
国が明治となってより後にも、町村の祭礼の行列には、必ず昔ながらの警護役という者があって、あるいは鉄棒を突き鳴らして前を払い、あるいはまた扇を開いて、四辺を制するような形をしていたものだが、しかも別になお紅い格好を染めた丸提燈などを手に持ち、靴をぎゅうぎゅう、洋剣をがちゃがちゃ言わせる人が若干名、群衆の中に交じっていて、実権は夙にそちらへ完全に移っていたのである。公共団体の制裁を統一し得る力が、鎮守の神に対する信仰以外において、別に儼乎として来たり臨んでいたのである。語を換えて言うならば、今回の塩竃事件のごときは、新旧警察力衝突の一個の事例に過ぎないので、その原因の明白なるはもちろん、世の中が改まるとともに、折合いが次第にむつかしくなったという点においても、すこしも意外または偶然の現象ではないのである。
(柳田國男「祭礼と世間」『東京朝日新聞』(1919年5月)、『柳田國男全集13』(1990年、筑摩書房))
柳田の民俗学は近代国家と民俗の軋轢に注目するのが実は特徴的なのだが、ここで柳田は反権力的な意味合いでの「祭り」への公権力の介入を批判しているのではない。「祭礼」に於いて「群衆」を誰がコントロールするか、という問題が存在するのだと、立論しているのだ。以前は祭礼を主催する側にその職能があったが、現在は警察官もそれを行っている。そして、警察の介入は、「神輿荒れ」という群衆の行動が公安上、看過出来ないとする。警察は神輿による破壊を氏子たちによる意思と解釈し、警察への乱入は、その意味で氏子の公権力への挑戦となる。暴徒化であり、まさに公安上の問題となる。当然、司法とは別に氏子たちが私的制裁を行うことも認め難い。
つまりここには、公権力によって制御出来ない「群衆」の登場が問題となっているのである。
実際、柳田は「群衆」という語をこの論考で用いているが、オルデガが『大衆の反逆』(1930年)で「群衆」を発見するのはもう少し後のことである。しかし、柳田はこの論考で明らかに「群衆」を論じているのである。
だから、『祭礼と世間』は群衆論として読めるし、読まねばならない論考である。
したがって柳田の問いはこう要約される。
しからばこの傾向をもって進むと、これから先どうなって行くのか、陸前塩竃様の神輿などは、いかなる指導者を得、その運動量とかは、どう統一せられることになるのかというと、それはまだ大いに考えてみないと何とも言われない。
(前掲書)
つまり「群衆」の「運動量」をいかにして「統一」していくのか、という問いである。
これは「群衆」をいかにして「社会」に作り替えていくかという問いである。そのことは何より、「祭礼と世間」という題名が明瞭に示しているといるだろう。「世間」とは柳田の議論の中ではこの後、常に「社会」に相当する語として用いられるからである。
その時、柳田は、「群衆」を意思のない物理的運動体とする日下部博士の主張と、他方では、意思はあるがあくまで「私怨」とする警察側の主張の双方に反証しなくてはならない。何故なら、柳田は「神輿荒れ」をかつての世論形成システムだと立証したいからである。
だから、柳田は神輿の暴走行為が氏子側なりの「公」であったことに議論を戻す。つまり「世間」という、村落共同体なりの「公」の発露であったと論じる。
日下部教授は否認せられたようであるが、祭の神輿舁きの悪意ということは、絶対に存在し得ぬものでもない。しかもそれがこの新しい世間において、始めて起ったというような、基礎の薄弱な風習ではなくして、平和なる前代の社会生活から、引き続いて相応に行われていたことは、自分等の容易く証明し得るところである。ただしこれと同時に考えねばならぬことは、この類の悪意が、果して宮城県警察のいわゆる、私怨を霽さんとするの挙であったか、あるいはまた公怨の結果であったかは、公を官、私を民と始めから決定して掛からぬ限り、そう簡単に判断し得る問題ではないということである。
(前掲書)
語を換えて言えば、普通に反することをするような人間を、すこしもいじめずにおくということが、公人としてもあるまじき事であった時代としては、この徒に対する祭礼の日の悪意のごときは、たとい少数の若衆頭の手でこれを表示したとしても、やっぱり、公怨でなければならなかったのである。だから我々は、よく時代を研究した上でないと、うっかり何事も言われない。時代は攻究しておくべきものである。
(前掲書)
日下部教授は純粋に物理的運動として神輿の暴走を分析したが、柳田はいわば、社会的運動としてこれを捉え直している。だからその行為の是非は別として、神輿による家屋の破壊は「私怨」でなく「公怨」であり、それを神輿によって実行する氏子はその点で「公人」である、と指摘する。
注意しておきたいのは、柳田がこのような形でこれからの公共性のあるべき姿を考えていた、というわけではないということだ。あくまで、「神輿荒れ」が表出した、かつての公共性のあり方、つまりかつての「祭礼」と「世間」の関わり方を検証しているのである。
こうして考えると、「神輿荒れ」は、村に於ける「公」と、近代に於いて警察が氏子にもとめる「公」という、二つの「公」の衝突であった、と整理できる。
ここで柳田は、神輿の暴走が、村なりの「社会」的制裁の意味を持ったフォークロアであるという議論の立証するため、祭礼の形を借りた社会的制裁の形式について具体例を示して行く。
ことに注意すべきは、この慣習に参与する者の、皆小児であったことである。この晩彼等は町内を巡り、「行跡の良からぬ事を、その者の背戸門の辺に来たり、同音に世間の見聞に与るところを、歯に衣着せず言い散らして、いずくともなく別れ去るなり」とある。その発端に「ざっとなざっとな、ここに話ありとな」と一人が言い、他の一人が「何とや」と受けると、それから罵倒を始めるのでこれをザットナと呼んだのである。
(前掲書)
そもそも祭礼の場とは、相互批判的な「ザットナ」が許されると柳田はいう。つまり、これは「公」的な制裁だというわけだ。このように祭礼とは「世間」という「公」が立ち現れる時空であると柳田は言いたいようだ。
そのうえで、中でも「ザットナ」の中心となるのは、しばしば小児であるとも指摘する。
ことに正月十五日のごときは、盆と亥子との二大節とともに、ほとんと子供デーといってもよろしいくらいの、子供を重んずる日であって、多くの場合には道路に立ち塞がって通行人に物をねだり、くれぬ時は繩を引っ張って通さず、または雑言をする。あるいは夜分人家の門を叩いて、餅や銭紙を貰いまわり、はなはだしきは花嫁の尻を打つがごとき無作法をあえてし、しかもこの日に限ってこれを制する者もないのが、近頃までの田舎の習いであって、わずかに学校の先生の尽力が、これを過去の物語となし得たのである。
(前掲書)
これなどは、殆どハロウィンの如き習俗であるが、小児の口を借りる形をとるのは依代としての子供に神が憑いて、いわば「神意」をもどくからだと柳田は言いたいのである。神輿の暴走もまた、祭りに於ける「ザットナ」であり、その意味で「神意」とみなされた可能性があるいうわけである。「神意」は神の名を方便とした公的制裁であり、つまり、「神輿流れ」は、かつての「公」の発露の形式だった。
その上で、次に、このような「公」は、神輿の物理的運動においてどう発露するのかを立論する。
次に批評してみたいのは、神輿を舁くところのいわゆる多人数が、果して日下部博士の想像のごとく、各人区々の心持をもって運動するものかどうか。交番の事件に寄りたる群衆と同じく、本来不統一の意思を積算したものに過ぎぬかどうかということである。
(前掲書)
つまり、日下部教授の言うように、神輿を担いでいる人々は全く個別のことを考え、単に物理的運動量の総和として制御不能になるのか、それともそこに集団の意志が何らかの形で表出し「神輿荒れ」となる仕組みがあるのか、という立論である。
そこで、柳田が注意をうながすのは神輿のか継ぎ手がだれかという問題である。柳田は神輿の担い手には二つあり、一つは「神人」と呼ばれる特殊な神職、もう一つは、氏子の中でも元服(成人)直後の「若い衆」が担ぐ例である。
塩竃は後者であるという。
神輿舁きの神聖なる任務は、まったくこの間の短い年限を先途とし、時としては最後の一年または二年を兄若い衆または、「年ばえ」などと名づけて、やや大きな権限を与え、たとえば前後の棒端を担いで方向を左右し、言語以外の眼付顔付をもって、仲間の年下を動かすものもあり
(前掲書)
15歳で成人して「若い衆」と呼ばれるが、「若い衆」の中でも年長者が「やや大きな権限」を持ち、その意志が反映し易い仕組みがあったとする。「若い衆」は、民意のいわば代表であり、彼らの担ぐ神輿の運動はそれゆえ、物理的法則の総和ではなく、彼らなりの意思の総和である。つまり、一見、暴徒に見えるが、自らを律し、「民意」を生成し、実行するのが「神輿荒れ」であり、ボイドの如く群衆が動くのではなく、そこに「民意」が発生すると柳田は考える。
このように、神輿の暴走は「群れ」の行為ではなく、「民意」の表明であり、「社会」の表出だと考える。
「祭礼」とは「民意」表出の場であるわけだ。
大塚英志寄稿:次のページ