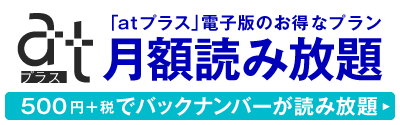もちろん柳田は一揆やその理由となった飢饉を記録することに意味がないと言っているのではありません。むしろ、その根本にある小作人たちの貧困を「社会問題」として位置付けようとしたのが柳田の立場でした。柳田の学問に「社会問題」の解決のため「社会」という主体を立ち上げようとしたと言っていいでしょう。
ですからここで彼が言っているのは、あくまでも「歴史」は特異な出来事、つまり、動乱や戦争、あるいは天変地異といった「異常事件」によって形作られるのではない、ということです。
例えば、私たちは今も大きな出来事を境に「歴史が変わった」と言いたがる傾向にあります。2000年代初頭は「9.11」、つまりアメリカでの同時多発テロで世界は変わったと多くの現代思想家たちが熱心に語りました。しかし、いつの間にか3桁の数字によって示唆される「歴史が変わった」重要な出来事は「3.11」、つまり東日本での地震と原発事故に取って代わりました。海外の学会などに行くと、かつて9.11に饒舌だった顔ぶれが、今度は「3.11」に饒舌だという光景に結構遭遇します。韓国では、セウォル号以前・以降という言い方が同じニュアンスで使われます。
確かにこれらの出来事で当事者たちの人生は大きく変わったでしょう。そのことを少しも軽視はしませんし、これらの出来事を正確に記録し、その原因をそれこそ「公文書」で洗い出し、同時に後世が判断する根拠を残していくのは重要です。テロや原発事故、遭難事故に至るまでにはアメリカや日本や韓国という国のそれぞれの為政者の不作為の積み重ねがあり、それが「公文書」に記録されていなくてはなりません。
しかし、災厄によってそれまでの歴史がチャラになり、何か良い意味でも悪い意味でも「新しい世界」が始まったと考えるのは、そこに至るまでの積み重ねを見え難くします。災厄の記憶を残すことには多くの人は熱心ですが、それをもたらしたり自体を悪化させた不作為の連続は「災厄」史観ではしばしば、忘却されます。
そして、このような「異常事件」を歴史の転換と考えると、当然、その困難に立ち向かう「英雄」的登場人物が必要とされます。「英雄」がいる以上、必然的に災厄の要因もまた特定の個人、つまり「悪役」に収斂します。
ぼくはかつて「9.11」からイラク戦争終結に至るまでのニュースで報じられている出来事の進展がハリウッド映画の脚本入門書に書かれた「文法」を正確になぞるように展開したことを指摘したことがあります。(参照 『サブカルチャー反戦論』)
これは、誰かが「9.11」の脚本を書いているからではなく、人々がそのような歴史を望み、メディアがそれに応えたからです。ニュースという日々の記録が「災厄」と「英雄」の歴史に容易に収斂してしまう一例です。ですからイラク戦争が根拠なき戦争であったことや、「9.11」とイスラム国の台頭が一つの歴史的な文脈の中にあったことも、この「災厄と英雄の歴史」観に立つと省みられないわけです。「3.11」も自民党の原発政策の長きに渡る不作為が原因ですが、なんとなく、菅直人を「悪役」とすることで、安倍晋三が、災厄から日本を救った「英雄」というイメージになっているのも同じです。
このように私たちは「英雄と災厄の歴史」を望みます。それは資料の厳粛な積み重ねという手続きを抜きに、「物語」(これは比喩でなく「物語構造」という意味です)として、「歴史」を理解します。「物語」は事実の立証の必要はなく、物語の構造に従ってキャラクターと出来事を配置すればいいわけです。
ですから私たちは「困難」や「危機」をことさら強調し、「敵」を名指しし、そこに「英雄」的に立ち向かう「為政者」にひどく弱いのです。
'80年代に現代思想家たちが「歴史の終焉」、つまりポストモダニズムの到来を宣告したにも拘わらず、サブカルチャーの領域では何故か「大きな物語」を内包するものがふえたのは、人々が歴史の不在に結局は耐え難かったことの証しとして、それがいわゆる陰謀史観や歴史修正主義と連なっていくものなのだ、ということはこの国の内でも外でも繰り返し話してきたのでここではもう書きません。(参照 Conference Proceedings 2015 vol III - IAJS/イスラエル日本学会)
しかし、今、私たちが「歴史」と思い込んでいるのは、このような「英雄と災厄」の物語のことです。「公文書」が例え為政者の記録であっても、それが不都合なことも含め正しく記録してあれば、そこから抜け落ちる領域があったとしても、相応に正確な歴史が描けるわけです。だから公文書改竄に問題がないと考える人は歴史に根拠などいらない、ただ心地よい物語であってくれと言っているに等しいわけです。
Web上に跋扈する陰謀史観や歴史修正主義は「歴史」ではなく「物語」であり、しかし、問題なのはそういう歴史ではない歴史に至る道筋が見えないからです。
話を戻しましょう。先の引用から、柳田は「文書」から立ち上がる歴史は偉人や英雄がつくり、特異な出来事の連続によって成り立つものに偏りがちだ、と考えていたことがわかります。実際には歴史上の「公文書」は税の記録など現在の「公文書」と同じく単調で退屈なものが大半です。ですから、これは「公文書」というよりは「歴史」に対する私たちの「思い込み」への警鐘と言えます。
それでは「歴史」はどこにあり、何よりどのようにして私たちはそれを獲得することができるのでしょう。改めて、そう「問い」を発してみましょう。
それを可能にすることが、柳田國男の「名付けられない学問」づくりの目的でした。
既に柳田が①国家や為政者の歴史ではない歴史 ②英雄と異常事件からなる歴史ではない歴史を構築しようと考えていたことは示しました。そのためには「公文書」を中心とする文字資料では限界があると考えていたことも確認しました。
では、そもそも柳田は一体どのような歴史を「歴史」と考えていたのでしょう。
柳田はそれを「世の常の推移」と形容します。いわば、日常の歴史、です。しかもその「日常」も普通の人々、庶民とか民衆とか大衆とか人民とか、呼び名は様々ですが、柳田は便宜的に「常民」と呼びました。これは階級的に「普通の人々」であると同時に「常」、つまり、日常を生きる人のニュアンスを見てとっていいかもしれません。
その柳田が考える「常民」の「日常」の歴史は例えば以下のようなものです。
たとえば日本人が飯を食い米の酒を飲むのは、古い習慣だなどと議会人は言って居る。ところがその飯はいつとなく無闇に白くなっただけでなく、蒸して炊いたイヒは式の日に限られ、日常は水で煮たカタカユを食うようになった。そうしてその柔かさも時と共に変ったと見えて、匙(さじ)のような中窪であった飯杓子が、全国を通じて今は板同然の飯切りとなってしまった。また酒が透明な液体になったのも、僅かに二百年来の変化であった。ひとり酒そのものの色彩に新たな統一が行われたばかりでなく、これを用いる機会方法、理由までが改まってしまった。これでも判るように古来の風というのは名前の運んだ本の心だけで実質は幾変りにも変遷を重ねているのであった。(中略)時の力は例外なく働き、こうした毎日の常不断の生活も尚その通りであったのである。
(同)
米の炊き方が変わることで杓文字の形態も変わって行く。私たちがずっと変わって居ないと思っている「日常」は「実質は幾変りにも変遷を重ねている」のだとときます。「日常」は、「サザエさん」一家の生活が変わらないように、どこか無時間だという感覚があります。しかし「日常」はゆっくりと推移していくのであり、それが「歴史」なのだ、と柳田國男は考えます。
しかし、このゆっくりとした日常の変化、つまり歴史はそもそも公文書の記録の対象にもならず、英雄や災厄からなる歴史観からもこぼれ落ちます。何より「日常」とことばで言うのは簡単ですが、それをそもそも実感することが困難です。この、米や酒の一例だけでも実際は釈然としませんよね。
だからこそ、それを可能にする「方法」の確立が柳田の学問の基本にあります。「日常の歴史」が実感しにくいなら、それを可能にする方法、つまり「学問」を彼は作ろうと考えました。
かつて、柳田國男の民俗学はしばしば「方法なき学問」と批判されてきました。柳田という天才の直感によって全てが支えられていて学問として万人が参画できる「方法」がない、という批判です。
それはしかし、殆ど言いがかりのようなものです。
柳田國男の学問はその「方法」の確立と共有こそが目的です。
この「方法」で「日常の歴史」を描くのは「研究者」でなく、あくまで「常民」です。このように自らが歴史を描き、それを共有することが、民主主義を可能にする「選挙民」の教養(つまり、思考の基準)なのだと柳田が考えて居たことは、繰り返しお話ししてきました。柳田は彼の学問を「読み書き算盤」的な主権者の技術であるべきだ、と考えていたわけです。その意味で柳田の学問に「専門の研究者」は存在しないのです。ここが他の学問との違いです。
柳田の「方法」が、しかし「ない」と批判されてきたのは、柳田の考えていることがあまりに早すぎたからです。そのことを柳田が考える「歴史」の書き方のお手本としては上梓した『北小浦民俗誌』を手がかりに考えてみましょう。昭和24年に刊行された同書の序文に「過去を明らかにしようとする希望が、普通教育の面において、一般に非常に高まって来ている」つまり、戦後教育の中で「歴史」をいかに生徒たちに学ばせるか、その機運に応えるものだ、と柳田は言っています。その意味でこの時期、柳田が拘泥していた社会科の教科書作りとリンクします。柳田は彼の学問を「社会科」化しようと模索しており、それは「社会」(歴史や地理や経済を含む「世界」)の「味方」を学ぶものでした。ですから『北小浦民俗誌』を読む上で重要なのは、その「方法」を読む、ということです。
ここで『北小浦民俗誌』について少し説明しておきましょう。この書はいくつかの批判にさらされています。同書は、柳田の弟子の倉田一郎が新潟県佐渡島の小村・北小浦で行なった民俗調査のノートを元にして書いたものです。これに対し、柳田は北小浦を船上から一瞥しただけで現地にも行っていない、という批判があります。あとがきで柳田は「北小浦とは舟から見て通った」だけで「知りたいと思うことは何一つ聴かれ」なかった、だから、倉田に調査してもらった、と隠すことなく述べています。弟子に調査させて自分は本だけを書く、いいとこ取りではないかというわけです。しかし、『北小浦民俗誌』は「全国民俗誌業書」の一冊として刊行され、他の本の著者は在野の研究者や柳田の弟子たちです。調査をやった倉田は故人です。
こういった、柳田は弟子たちの資料を収奪した、という批判がアカデミック化した学問からの批判は、調査を含め研究の成果を自身の研究者としてのキャリアにすることが当然のアカデミシャンの考え方が前提にあることに気がつくべきです。
そもそも柳田にとって「研究」とは「個人」で行なうものでなく、共同で行なうもので、しかもそこに参画するのは専門の研究者でありません。柳田へのこの種の批判をしてきた人々がアカデミアの人々であることは注意していい問題です。
また、こういう批判もあります。『北小浦民俗誌』の元になった倉田一郎の調査は昭和12年、つまり日中戦争勃発の年になされています。倉田が柳田に提出した調査ノートに「戦時色」がない、という批判です。しかし、倉田は当時、ナチスドイツ型国策民俗学に心酔した一文を残していて、その彼が「戦時色」を出せば、どういう記述となったかは明らかです。柳田は、「異常事件」の記録でない歴史を描くという構想を日中戦争以前から明確に示していて、それは十五年戦争下も戦後も一貫しています。この倉田の調査はこの時期、柳田が初めて行った大掛かりな全国規模の民俗調査の一部です。柳田は昭和12年に刊行したこの調査の報告書の一つに、狩猟文化の中に内在する「殺生の快楽」が戦時下という異常に暴走するリスクを示唆しています。それはあたかも南京虐殺の予見であり、事件後もその記述は削除されていません。(詳細は、大塚英志『戦争と殺生の民俗学』参照)
戦争という「非常時」の歴史は「日常」の歴史を知ることで初めて理解できるわけです。
まして、柳田は「戦後のことば」として『北小浦民俗誌』を上梓したのであって、柳田が同書で「戦時下」を隠蔽しなくてはいけない理由はないのです。
大塚英志寄稿:次のページ