太田出版ニュース
1
【1995年刊「クイック・ジャパン第3号」掲載・小山田圭吾氏インタビューに関しての弊社編集者・村上清コメントを掲載します】
「クイック・ジャパン第3号」に掲載された「いじめ紀行」の記事を取材・執筆した村上清は、記事が掲載された時点では外部の新人ライターであり、太田出版が出版社の判断として特集を認め、記事を掲載しました。村上はその後太田出版の社員となり編集部員として現在に至りますが、もとより当時の村上本人に決定権があったわけではありません。今回の問題は、執筆者一人に帰すべき問題ではなく、まず出版社の問題であり責任です。そのため太田出版からのお詫び、考えを述べた文章を2021年7月19日に弊社ホームページに出しましたが、村上個人が表に出ることは控えさせてきました。
この度、9月16日付「週刊文春」で小山田氏のインタビュー記事が掲載されたことを受け、村上より当時の状況、当時の考え、時間がたっての現在の反省を伝えたいという強い希望が新たにありました。本人の希望を了解し、以下に村上からのコメントを掲載いたします。
2021年9月16日
株式会社太田出版
社長 岡 聡
* * *
1995年執筆記事「いじめ紀行」に関しまして
1995年刊『クイック・ジャパン第3号』掲載「いじめ紀行」取材・執筆者の村上と申します。同連載第1回・小山田圭吾さんインタビュー記事に関して、多くのご意見、ご批判を頂いてきました。
まず何より、記事中で触れている、当時のいじめ被害にあった方々やそのご家族の方々に対して、著しく配慮を欠いた記事執筆をしたことを深くお詫び申し上げます。また記事中に「障害がある人」と明記しながら、その方々がどう生きているかに対する意識が執筆時に全く抜け落ちていたことも、大変今更ながら認識致しました。これは非難されて当然であり、執筆者の未熟の極みと言う他ありません。本当に申し訳ございません。また近年、いじめる側の勝手な論理としてよく伝えられる「いじめてるんじゃなくて、いじってる」を想起させる描写を無配慮に掲載していたことも、恥ずべきだと思いました。重ねてお詫び申し上げます。
当時の経緯をご説明いたしますと、本記事でいじめを支持したり、ましてや称揚する意図は、当初から全くありませんでした。執筆当時、すでに痛ましいいじめ自殺の報道が繰り返され社会問題化していましたが、それが一向にやまないどころかいじめの手口が巧妙に「進化」する様を見るにつれ、小中学校時代にいじめを受けた経験のある自分は怒りや虚しさを通り越し、一種呆気にとられるような言い難い感情に至ったことが執筆の発端にあります。そこから、「いじめはいけない」「いじめはやめよう」といった、正しいけれど素朴な言葉をどれだけ重ねても現実のいじめはなくならないのでは、という苛立ちが募った末、あえて極端な角度からいじめという重大な問題の本質を伝えることで事態をゆさぶり、何らかの突破口にできないかと思うに至りました。
記事中にも書いております通り、もともと本企画は「いじめた側といじめられた側の対談」という趣旨でした。しかし今思えば当然なのですが、「いじめられた側」の方に応じていただくことが叶いませんでした。対談という形が不可能になり、それでも一方の立場の方からのお話は、こちらのお願いを汲んで聞かせて頂けることになった時、記事の主眼を意識的に「いじめた側にはどんな風景が見えていたのか、どんな考えを持っていたのか」に置くことにしました。
私の勉強不足もありますが、当時、いじめる側にも立っていた人の言葉というものを活字でほぼ見たことがなく、断罪を前提としない状況でその言葉をインタビューし記録することは、(非常にセンシティブなことは論をまちませんが)前述の”あえて極端な角度から「いじめ」の本質を伝え、突破口とする”に合致すると判断しました。それが、いじめのディテールを一方的かつ克明に描写することに繋がっています。さらにその話を聞いている筆者も笑っている、とわざわざ書き加えたのは、私自身「いじめられる側」であっただけでなく「傍観者」だった時期もあることから、自分もその残酷な構造に加担しているということも、最低限、活字に残さなければいけないと考えたためです。
だからこそ一方で、記事後半にある”いじめられた方々の「その後」”は、取材でわかった範囲だけでも絶対に書かなければならないとも思っていました。
ではそんな文章を書いて当時誰に読ませたかったのかといえば、主に、全国に今も存在するだろう無言の「いじめ加害経験者」や私自身含む「傍観者」に対してだったと思います。「学校」という本来は学びの空間でも、人間は時にあまりに無自覚に暴力的になりうる、それは日常的に行われうるのだということを、鏡のように彼らに突きつけたかった。記事原文では冒頭から私の露悪的な文章が続きますが、それは本来の対談相手でもない筆者が「いじめはよくない、やめよう」と書いたり態度に示すことは、彼らにとっては一気に、安心できる教科書的記事になってしまい、それでは何も伝わらない、毒には毒をもって対するしかない、と当時考えたためです。
くわえて、談話者である小山田さんにこの内容を公の場で語ってもらうことになる以上、聞き手(書き手)も同等に「悪質」でなければ不誠実だという意識もあり、通常の意味でのバランスを取った記述はしない、という選択を意図的にしました。これは今振り返れば皮肉と反語を掛け合わせたような意識、記述形態なのですが、読む側にしてみれば意味不明、と言われれば返す言葉はございません。
記事中に「いじめってエンターテイメント!?」という私の記述があります。これも皮肉・反語ですが、そうでない形で書き直すならば、「いじめにあたる行為や場面を娯楽、ショーとして消費してしまう性質が、人間には(善悪の判断以前に)どうしようもなく潜んでいる」という文言になります。その認識を出発点にすることでしか、いじめという「現実とは思えない現実」の輪郭にたどり着けないと、当時考えていました。
今回、本記事の「原文」としてネット上で最も参照されたであろうブログの記事が必ずしも元記事原文のままではなく、少なからず削除・切り取りされたものであったことは、今夏のオリンピックのタイミングで知りました。いち執筆者として率直に申し上げれば、センシティブなテーマを扱ううえで当時の自分としてぎりぎりの神経を使って言葉を配した箇所ほど狙ったようにカットされていたことは確かです。前述の皮肉や反語という文脈、そして談話者の取材現場での語り口にあった一種の諦念、自虐といったニュアンスが削ぎ落とされたテキストが、今回多くのケースで「原文」として参照されたということは、記事の取材・執筆者としてここに記させて下さい。現場での小山田さんの語り口は、自慢や武勇伝などとは程遠いものでした。また原文記事の最終頁に小山田さんの同級生だったSさん(仮名)の年賀状が掲載されていますが、これも当初から「晒して馬鹿にする」という意図は全くなく、元記事全文の様々な文脈を経て終盤で語られる、Sさんと小山田さんの間にあった不思議な交流、友情の挿話に即して掲載されたものです。
ただ繰り返しますが、そもそも削除・切り取りのない本来の原文自体、執筆者として今見ると大変配慮を欠いたものであったという認識は変わりません。
本記事(「いじめ紀行」)は、上述の執筆動機をふまえ、本記事を第1回として以降シリーズ化し、各界で影響力のある方々や、いじめをテーマとした作品を創っているクリエイターの方々の過去のいじめ体験(加害、被害、傍観いずれの立場からも)のインタビュー/ノンフィクション記事集として単行本にまとめられないかという構想もありました。しかし筆者の力量不足から数回の連載で中途半端に終了しました。センシティブなテーマに手を出したものの十分な掘り下げを行なえないまま、結果としていじめ被害を受けた方々をフォローする記事も作れませんでした。あくまで「当方提案企画の第1回ゲスト」でしかなく、また記事中にもあるように当初はこの取材を断っていたにもかかわらず、こちらの懇願を見かねて応じてくださった小山田さんの回のみが後々まで前面化する形になったことも、取材・執筆者である私自身の未熟さ、限界の証であると考えています。
当該記事は当時フリーライターだった私の商業誌で最初の執筆であり、その後同誌編集部に1998年までの約3年間参加していましたが、現在、私は同誌の内容には一切関係しておりません。現編集部は今回の事態を認識したうえで、日々検討しながら新たな誌面を制作しております。
同誌編集部を離れて以降、私は同じ刊行元である太田出版の書籍編集としてゼロから今に至るまで勉強し直している途中です。当該記事発表からのこの26年間に、いじめられる側や障がいを持った方々をテーマとする書籍を企画編集させて頂く機会に幸運にも幾度か恵まれました。そこで得た学びは何ものにも代え難いものでした。それが免罪符になるとはもちろん思いませんが、今回、多大な気づきの機会を頂けたこともふまえ、今後もこの仕事を通して少しずつでも贖罪を重ねて参る所存です。
最後にあらためまして、本記事での配慮を欠いた記述を目にして傷つかれたいじめ被害者の方々やそのご家族の方々、そして読者の方々にお詫び申し上げます。
そして、今もこの国の様々ないじめの現場で実際に汗を流し、いじめを防ぐことや被害者の方の社会復帰に尽力されている方々に対しても、深いお詫びと、心からの尊敬の念を記させて頂きます。
2021年9月16日
太田出版書籍編集部
村上清
1









![Club OH[クラブ・オー] - 太田出版の無料会員サービス](http://www.ohtabooks.com/common/img/bnr_cluboh.jpg)

 クイック・ジャパン
クイック・ジャパン 芸人雑誌
芸人雑誌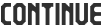 コンティニュー
コンティニュー GIRLS CONTINUE
GIRLS CONTINUE